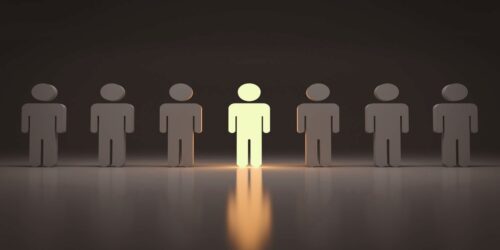調査ファイル
カスタマーハラスメント対策が法律で義務化!必要な措置や対策は?


読み終わるまで 6 分
「カスタマーハラスメントって法律で規制されてるの?」
「カスハラ被害にあってるけど、企業としてどう対応すればいいの?」
接客や顧客対応に携わる現場で、理不尽なクレームや暴言に悩まされている方も多いのではないでしょうか。
もちろん、顧客からの正当な意見や要望を受け止める姿勢は大切です。
しかし、「土下座しろ」「家まで謝りに来い」といった常識を逸脱した要求は、すでに苦情の域を超えたハラスメントです。
厚生労働省の調査では、企業に寄せられるハラスメント相談のうち、92.7%の企業がカスタマーハラスメントを経験していると回答しています。
多くの企業がカスハラに悩まされている現状を見ると、パワハラ・セクハラに次いで深刻な問題として、早急な対応が必要と言えるでしょう。
本記事では、カスタマーハラスメント対策の法律を知りたい読者に向けて、法整備の現状と企業に求められる対応策などをわかりやすく解説しています。
従業員と企業を守るために、まずは正しい知識を持つことから始めましょう。
目次
カスハラに関する法律はある?

カスタマーハラスメントを直接的に取り締まる法律は存在しません。
カスハラは企業にとって対応の難しい問題でありながら、現場任せで対応せざるを得ない状況が続いてきたのです。
しかし、カスハラは増加傾向にあり、早急な対応が不可欠です。
事実、厚生労働省が実施した職場のハラスメントに関する調査によれば、カスハラはパワーハラスメント、セクシャルハラスメントに次いで3番目に多いという結果が出ています。
また、過去3年間の推移においては、カスハラが「増加している」と回答した企業の割合が、「減少している」と回答した企業を上回っており、現場の負担が年々大きくなっている実態が浮き彫りになっています。
こうした背景を受けて政府は、2025年6月4日の労働施策総合推進法の改正に伴って、カスハラ防止に関する新たな法律の制定に踏み切りました。
企業にカスハラ対策の義務を課すことで、従業員を守り、働きやすい環境を整える法的基盤がようやく整おうとしています。
企業が講じるべき「カスハラ対応策」の義務8つ

ここからは、労働施策総合推進法の改正であげられている、企業が義務を負うカスハラ対策を8つ紹介します。
義務1:事業主の基本方針の明確化と周知
労働施策総合推進法の改正により、企業はカスタマーハラスメントに関する基本方針を策定し、全社的に共有することが義務化されました。
企業がカスハラへの指針を明確に示すことで、顧客対応の最前線に立つ従業員が「どのように動けばよいか」を判断しやすくなり、迷いや不安が軽減されます。
厚生労働省が発行している「カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル」では、基本方針に盛り込むべき内容として、以下の項目が示されています。
- カスタマーハラスメントの内容
- カスタマーハラスメントは自社にとって重大な問題である
- カスタマーハラスメントを放置しない
- カスタマーハラスメントから従業員を守る
- 従業員の人権を尊重する
- 常識の範囲を超えた要求や言動を受けたら周囲に相談してほしい
- カスタマーハラスメントには組織として毅然とした対応をする
引用:カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル|厚生労働省
カスハラへの方針を文書として明文化し、社内に広く周知していくことで、従業員に的確な対応を促せます。
また、従業員を守るための意識と行動を組織全体に根付かせるきっかけにもなるでしょう。
義務2:従業員のための相談体制整備
企業が講じるカスハラ対策義務として、カスタマーハラスメントを受けた従業員が相談できる体制を整えることもあげられます。
従業員が相談しやすい体制を作ることで、カスハラの発生や実態を早急に認識し、対策を立てることが可能です。
具体的には、社内に相談窓口を設けるか、現場を日常的に把握している上司を相談対応者に任命することが必要です。
なお、専用窓口を新設するのが難しい場合は、既存のパワハラ相談窓口や社内ヘルプラインなどを兼用する方法でも構いません。
最も重要なことはハラスメントに対して相談できる体制を整え、従業員が安心して働ける環境を構築することです。
義務3:カスハラへの対応方法を策定
企業には、カスタマーハラスメント(カスハラ)への具体的な対応方針の策定が義務づけられています。
厚生労働省が公表している手引きでは、カスハラの典型的な9パターンが提示されており、それぞれに適切な対応例が示されています。
これらのパターンは、初動対応の指針や社内マニュアルの整備に活用でき、現場での対応の判断基準としても有効です。
| 型の名称 | 概要 | 想定される対応策 |
| 1. 時間拘束型 | 長時間の居座りや電話を切らない行為など | 応じられないことを明確に伝え、退席や通話終了を求める。必要なら警察に連絡。 |
| 2. リピート型 | 同じ要求を繰り返す、過剰な連絡 | 応対を控える旨を伝達し、記録を残したうえで窓口を一本化。冷静に対処。 |
| 3. 暴言型 | 大声、侮辱的発言、名誉毀損的な言動 | 録音によって記録し、悪質性に応じて退場を求める対応を検討。 |
| 4. 暴力型 | 暴行、物を投げるなど身体的危害 | スタッフの安全を最優先に、警備・警察と連携して対応。 |
| 5. 威嚇・脅迫型 | 殺害予告やSNSでの拡散をほのめかす発言 | 複数人で対応し、必要に応じて法的措置を検討。 |
| 6. 権威型 | 地位を盾に土下座を強要するなどの無理な要求 | 担当者を変更し記録を残す。迎合せず慎重に対応。 |
| 7. 店舗外拘束型 | 店舗外(喫茶店・自宅など)への呼び出し | 単独での対応を避け、対応の可否と方法を明確にする。 |
| 8. SNS・ネット中傷型 | ネット上での誹謗中傷や虚偽の書き込み | 削除要請や発信者の特定手続きを取り、必要に応じて弁護士と連携。 |
| 9. セクハラ型 | 不適切な接触や性的発言 | 録音・録画を行い、事実確認のうえで厳正な対応を取る。 |
上記のような典型的な事案ごとに社内で対応フローを整えておくことで、現場の従業員が迷うことなく落ち着いて行動できます。
さらに、組織として一貫性のある対応をとることで、「この企業には通じない」という印象を与え、悪質な行為を未然に防ぐ効果も期待できるでしょう。
義務4:社内対応ルールの従業員への教育
カスハラへの対応策を策定したあとは、社内ルールを周知するために従業員の教育が必要です。
どれだけ対応ルールを整備しても、現場の従業員が内容を理解し、実践できなければ意味がありません。
教育内容には、経営層からのメッセージや社内で定めた対応マニュアルを含め、実践的な項目を盛り込むのが効果的です。
例えば、以下のような内容が想定されます。
- 悪質なクレーマーの定義
- カスタマーハラスメントに該当する言動の具体例
- パターン別の対応方法
- 苦情対応の基本的な流れ
- 接客の心構えや言葉遣いのポイント
- 対応記録の作成方法とその重要性
- 発生した事案をもとにしたケーススタディ
また、従業員だけでなく経営層や相談対応者に対する研修も欠かせません。
とくに経営層にはカスハラが事業へ及ぼす影響や、迅速な意思決定の重要性について理解を促す必要があります。
経営層がカスハラに対して理解を深めていかないことには、組織的な体制づくりが進まないためです。
組織全体でカスハラに対応するために従業員と経営層分け隔てなく、理解を深めていきましょう。
義務5:事実関係の正確な確認と対応
実際にカスハラが起こってしまった場合は、事実関係の正確な確認と対応が不可欠です。
事実確認ができなければ、顧客の訴えが正当なものなのか、あるいは一方的な言いがかりなのかを見極められません。
厚生労働省が定めるマニュアルのなかでは、次の流れで事実か確認を行なうことが望ましいとされています。
- 時系列に沿って、起こった出来事を把握する
- 顧客が求めている内容を整理する
- 要求の妥当性を検討する
- 要求の手段や態度が社会通念上許容できる範囲か判断する
引用:カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル|厚生労働省
上記の確認作業を経たうえで、カスハラに該当する行為であると判断された場合には、事前に策定した社内の対応基準に従って行動します。
場合によっては責任ある立場の者から退店を求めたり、今後の出入り禁止を通告したりといった対応も検討されます。
義務6:従業員への配慮の措置
カスタマーハラスメントの被害を受けた従業員に対して、身体的な安全確保と精神的なケアを速やかに行なうことも義務化されます。
例えば、暴力行為やセクハラ行為があった場合には、現場責任者が顧客対応を交代し、被害を受けた従業員をその場から引き離すことが必要です。
状況に応じて複数人で対応したり、弁護士や警察と連携し、安全を最優先に確保する対応も求められます。
また、精神的なダメージが見られる場合には、産業医やカウンセラー、臨床心理士などの専門家と連携してアフターケアを行います。
必要に応じて医療機関の受診を促し、ストレスチェックなどを通じて従業員の心身の状況を継続的に把握していくことが重要です。
カスハラへの対応は、単に問題を処理するだけでなく、被害者の心に寄り添った配慮を行なうことが欠かせません。
義務7:再発防止の取り組みを行なう
カスタマーハラスメントの問題が一度解決しても、再発防止の取り組みを行なうことが重要です。
再発防止策を講じなければ、また同様のカスハラが起こり、従業員を危険にさらす可能性があるでしょう。
カスハラに対する具体的な再発防止策としては、以下のような取り組みが行われています。
- 朝礼などの場でトラブル事例を全従業員に共有
- 事案ごとの報告書を作成し、関係部署と情報を共有
- 多発する事例は勉強会を開催し、対応の質を全体で底上げ
- 実際のトラブル事例を個人情報に配慮した形で文書化しマニュアルに反映
再発防止策を継続的に取り組むことで、従業員の接客力向上だけでなく、企業全体の対応力強化へとつながります。
義務8:その他の取り組み
カスタマーハラスメントの予防と解決を進めるうえでは、従業員のプライバシー保護や相談環境の整備、取引先との連携も含めた包括的な取り組みが必要です。
例えば、「相談したことを理由に不当な扱いは行わない」旨を明文化し、従業員が安心して声を上げられる環境を整える必要があります。
加えて、カスタマーハラスメントの発生を迅速に把握する体制も整備しておくべきです。
従業員からの相談を受けるだけでなく、以下のような兆候を早期に察知する仕組みがあることで、問題が深刻化する前に対応できます。
- 緊急時に専門部署へ即時報告できる体制を設ける
- 現場責任者がすぐに情報を共有する
- 顧客との通話内容の文字化システムを活用する
- 年に複数回の面談を通じて現場の声を吸い上げる
他にも、カスタマーハラスメントは顧客だけでなく、取引先企業との間でも起こり得るものです。
仮に自社従業員が取引先でハラスメント行為を行った場合には、事実確認への協力を拒まない姿勢が求められます。
調査の必要がある場合は、弁護士など中立的な立場の第三者に委託することも一案です。
このように、ハラスメントの予防と対応においては、個々の事案に対応するだけでなく、組織全体で風通しの良い環境と被害者への配慮を育む姿勢が求められます。
企業がカスタマーハラスメント対策を怠った場合のリスク事例

ここからは、企業がカスタマーハラスメント対策を講じないリスクを解説します。
対策が不十分で損害賠償が認められた事例
企業や組織がカスタマーハラスメントへの対応を怠ったことで、損害賠償責任が認められた例として、市立小学校での裁判事例が挙げられます。
本事例では、教員が児童の保護者から不当な言動を受けたにもかかわらず、校長は教員側に非があると決めつけるような対応を取りました。
さらに、実際の状況や背景を十分に調査しないまま、教員に対して保護者への謝罪を促し、場を収めようとしたのです。
裁判所は、この一連の対応が教員に対する不適切な取り扱いにあたるとし、校長の行為を不法行為と認定しました。
最終的には、学校を設置していたA市と給与を支給していたB県の双方に対して、損害賠償の支払い義務があるとの判断が下されました。
このように、カスハラが疑われる状況で組織が安易な判断を下すと、被害を受けた職員を守れないばかりか、法的責任を問われるリスクも発生します。
適切なカスハラ対策を講じることは、従業員を守ると同時に、組織としての信頼性や社会的評価を維持するためにも必要不可欠です。
対策していたことで損害賠償が認められなかった事例
一方で、企業がカスタマーハラスメントへの対応体制を十分に整備していたことにより、損害賠償責任が否定された判例も存在します。
このケースでは、小売店の従業員が顧客とのトラブルを経験したことを受け、会社に対して「安全配慮が不十分だった」として損害賠償を求めました。
しかし、裁判所は以下の対応が適切に実施されていたことを認め、企業の責任はないと判断しました。
- 入社時にクレーム対応に関する教材を配布していた
- 苦情対応の初動についての指導を行なっていた
- サポートデスクや近隣の店舗責任者に即時連絡できる体制を確保していた
- 深夜帯でも常に複数名で店舗を運営する体制を敷いていた
上記判例のように、企業が平時からカスハラに備えた仕組みを整えておくことは、予期せぬトラブルに対して法的責任を回避するための備えにもなります。
従業員を守る仕組みづくりは、そのまま企業のリスク管理としても機能するのです。
探偵が「証拠収集」でカスハラ対応を支援できる理由
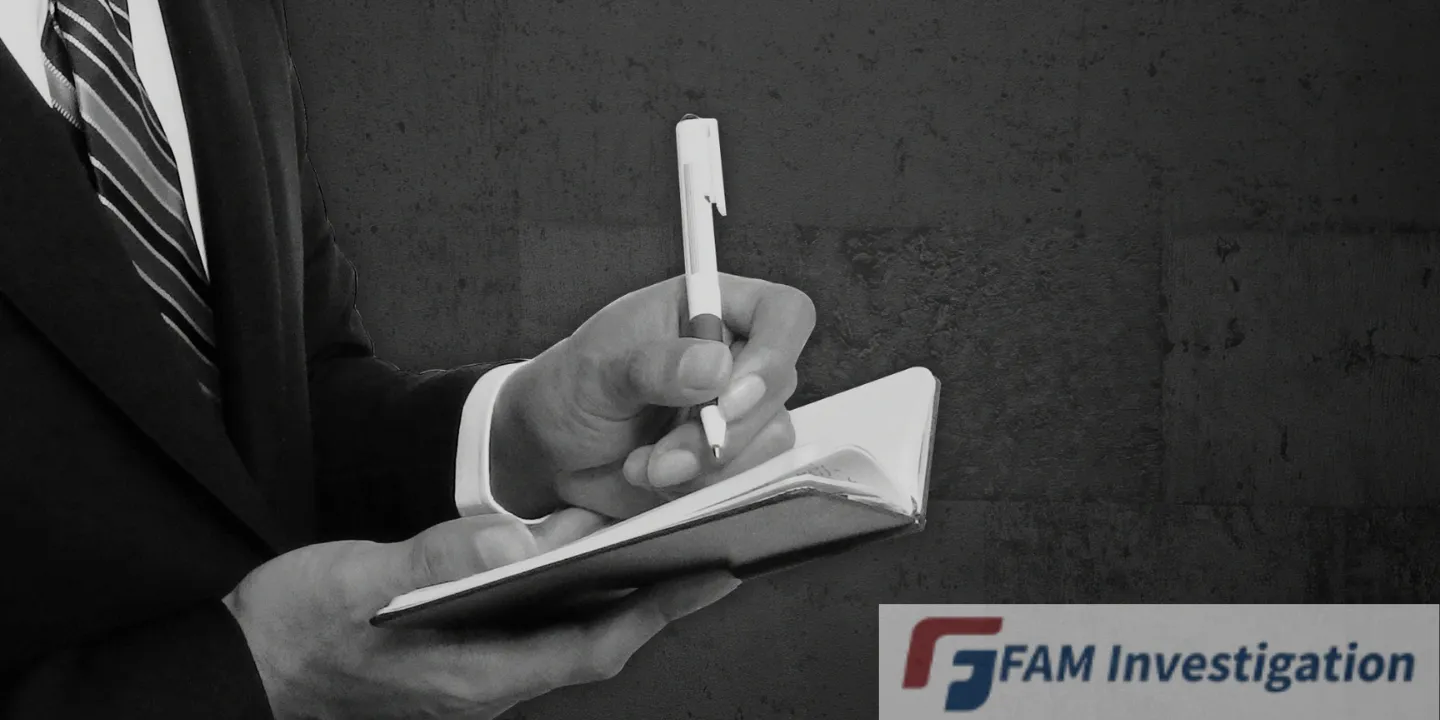
企業がカスハラに対応する際には、状況に応じて弁護士や警察の協力を仰ぐケースもあるものです。
しかし、これらの公的機関と連携を図る際には、カスハラに該当する証拠が求められることもあります。
カスハラ対応で必要となる証拠収集には、探偵の利用がおすすめです。
ここでは、カスハラ対応の支援に探偵を利用すべき理由を解説します。
合法的に証拠を収集できる
探偵を利用するとカスハラの証拠収集を合法的に行なえます。
カスタマーハラスメントに対して毅然と対応したくても、証拠の収集方法を誤れば、企業側が逆に訴えられるリスクがあります。
例えば、以下のような対応は違法行為と見なされる可能性が高いため、注意が必要です。
- 顧客の店舗外での行動をこっそり撮影
- ハラスメント電話を勝手に録音し、内容を第三者に漏らす
- 複数回の来店記録を基に、相手の居住地を特定しようとする
店外での撮影や相手の居住地等の特定は、たとえ相手がカスハラ加害者であっても、プライバシー権の侵害や名誉毀損、盗聴・盗撮等に該当する恐れがあります。
探偵事務所であれば、個人情報保護法などの法律を遵守しながら、音声・映像記録、嫌がらせ行為の発信元特定、接触頻度の記録などを合法的に取得可能です。
「証拠があるはずなのに使えない」「訴えたのに企業側が悪者にされる」といった事態を避けるためにも、専門家のサポートを検討すべきです。
企業には難しい事案にも対応可能
探偵は、企業内では対応が難しい、複雑かつ継続的なカスハラ事案にも対応できます。
とくに以下のような、誰が加害者なのか明確でない場合や、執拗に繰り返される嫌がらせ行為において、専門的な調査スキルが大きな力を発揮します。
- 退職した元従業員が、別人を装って執拗なクレームを続ける
- 匿名のメールや投書で従業員や企業の名誉を傷つける行為が断続的に続いている
- 被害の訴えがあるが内部では証拠もなく「対応のしようがない」と放置されている
カスハラの加害者が不明なケースでは、探偵が行動調査や発信元特定、証拠の収集と記録化を行って、加害者と事実関係を特定することが可能です。
探偵の専門性は、企業単独では対応が難しいカスハラ被害への突破口を開いてくれる存在です。
セキュリティ対策などをアドバイスできる
探偵はカスタマーハラスメントを「未然に防ぐためのセキュリティ対策」についても、実践的なアドバイスを行います。
例えば、次のようなカスハラ対策案を提示してくれます。
- 防犯カメラの設置場所・角度・台数の最適化
- 被害の記録を残すための映像・音声の保存体制の整備
- カスハラ対応のマニュアル化
また、継続的な嫌がらせや張り込み被害が想定される場合は、出入口の死角対策、警察との連携方法など、より高度なセキュリティ知識に基づいた助言も可能です。
探偵は証拠を取るだけではなく、カスハラが起きにくい職場環境そのものを設計するパートナーとしても、大きな役割を果たしてくれます。
探偵に依頼する前に確認したい3つのポイント

探偵はカスハラ対策に頼りになる存在ですが、闇雲に調査を依頼すべきではありません。
ここでは、探偵に依頼する前に確認すべきポイントを3つ紹介します。
カスハラ対応の実績があるか
探偵に依頼する前に、カスハラへの調査経験を持っているかを必ず確認しましょう。
カスハラへの対応は一般的な浮気調査や素行調査と異なり、企業のレピュテーションリスクや、従業員の心理的安全性を守る配慮が求められるためです。
探偵の初回相談時には、以下のような点をヒアリングするのがよいでしょう。
- 類似のカスハラ案件をどの程度扱っているか
- 調査結果が警察や弁護士の対応に活かされた事例があるか
- 顧客対応や職場トラブルに対する理解を持っているかどうか
さらに、「消費者トラブル」「脅迫」「威力業務妨害」といった広義のハラスメントにも対応できる探偵であれば、万が一問題が複雑化しても安心です。
調査の範囲と料金体系が明確か
カスタマーハラスメントの調査を探偵に依頼する際、調査の範囲と料金体系についても事前に確認しておきましょう。
不明確なまま契約してしまうと、調査範囲が思ったより狭い、想定より多くのコストがかかるなどのトラブルを招くリスクがあります。
例えば、調査対象が勤務時間中の接触行為のみとなっており、閉店後の待ち伏せやSNS上での嫌がらせについては対応してもらえないといったトラブルもあります。
失敗を避けるためには契約のタイミングで、調査する時間と場所、調査対象の行為などを明確に説明してもらうことが大切です。
また、合わせて調査時間単価や深夜帯の加算、成果報酬の有無など、料金の内訳についても丁寧に確認しておくと安心です。
探偵にカスハラの調査を依頼する際は、調査範囲と料金体系の確認は欠かせません。
プライバシー保護と守秘義務は徹底されているか
探偵にカスタマーハラスメントの調査を依頼するうえで、情報管理が徹底されている点も重要です。
調査依頼者である企業情報や、調査対象となる個人のデータが外部に漏洩すれば、それ自体が新たなトラブルを招きかねません。
具体的には、面談時に完全個室が用意されているか、顧客情報の保管・廃棄体制が整っているか、社内に情報管理責任者が配置されているかなど確認しましょう。
加えて、希望すれば秘密保持契約(NDA)を締結できるかどうかを確認しておくと、企業として盤石なリスク対策が可能です。
調査の質だけでなく、情報を「誰が・どこで・どう扱うか」まで見極めることが、安全かつ効果的なカスハラ対策へとつながります。
カスタマーハラスメントは法律に則って対策しよう

カスタマーハラスメント(カスハラ)は、パワハラ・セクハラに次いで多い深刻な問題として認識されており、法整備の必要性が高まっていました。
これまで一部自治体での条例はあったものの、努力義務にとどまり抜本的な対策とは言えませんでした。
今回、企業に具体的な8つの義務を課す法制度が整備され、相談体制や従業員教育などの取り組みが明確に求められます。
今後は法に基づいた対策を講じて従業員を守り、企業のリスクを回避していくことが必要です。
また、悪質なクレームの証拠収集や対応の限界を感じる場合には、探偵による支援を活用するのも一つの手です。
外部の力を借りることで、より安全かつ確実に問題解決を図れるでしょう。
ご相談とご依頼までの流れ
-
まずはフリーダイヤル・お問い合わせメールフォーム・LINEよりお問い合わせ下さい。問題の概要や状況をお聞き致します。
-
無料面談にて、電話やメール、LINEにて無料相談頂いた内容の詳細をお聞きし、お手伝い出来る調査やサポートをご提案致します。その際、お見積りをご提示致します。
お見積り内容には、調査期間・調査員数・調査方法・調査報告書の作成費などが含まれています。 -
お見積り金額・調査内容に十分ご納得頂けた場合、委任契約のお手続きに入ります。下記書面に署名捺印をして頂き、契約完了となります。書面には、調査目的・期間・費用の詳細・調査結果の報告方法・個人情報の取り扱いなどが記載されています。
-
契約書面を基に予備調査、本調査の順に調査を実施します。その際、随時途中経過をご報告致します。追加調査が必要な場合は、都度ご相談下さい。
-
全ての調査終了後、書面もしくはデータにて調査報告書を提出致します。必要に応じて各種専門家のご紹介やアドバイスなどのアフターサービスも行なっております。
お問い合わせ
ご相談は、プライバシー 秘密事項厳守で承ります。
クレジット決済のご案内
お支払い方法について、銀行振込のほか、各種クレジットカードにも対応しております。
ご都合のよい方法をお選びいただけます。
クレジットカード決済は、テレコムクレジット株式会社にて、おこなっております。
※ ご利用者様のクレジットカードの内容はSSLにて厳重に保護されます。
※ 提供サービスの特性上、決済後の返金はお受け出来かねます。