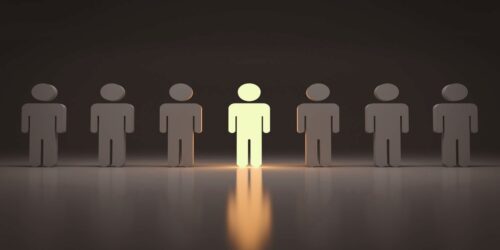調査ファイル
PCハッキングされたか調べる方法|被害に気づく5つの兆候とは


読み終わるまで 6 分
PCをハッキングされた場合、重要な情報が漏えいしたり、金銭的な被害を受けたりする恐れがあります。
どのような対策を講じるべきかを把握するとともに、ハッキングされたかどうか確認できることが重要です。
個人のPCがハッキングされたことによって、家族や会社にも被害が広がることもあります。
ハッキングされたサインを見逃してしまうと、甚大な被害に繋がる可能性が高いです。
本記事では、PCがハッキングされたか調査する方法や兆候について解説します。
ハッキングを疑っている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
PCへのハッキング被害の初期サイン

PCがハッキングされている場合の、初期兆候について解説します。
ここで紹介する症状がみられる場合、ハッキングが疑われますので注意してください。
急に動作が重くなる・ファンが常に回っている

普段はスムーズに動くパソコンが、突然動作が遅くなったりフリーズを繰り返すようになった場合、内部で不正なプログラムが動いていたりする可能性があります。
特に、ファンが常に大きな音を立てて回っているときは、CPUに過剰な負荷がかかっているサインかもしれません。
ハッカーはバックグラウンドで情報収集や外部通信を行うプログラムを仕込むことがあり、その結果としてパソコンの負担が増します。
ウイルスやマルウェアが原因であることも多いため、異変を感じたら稼働中のプロセスを確認することが重要です。
身に覚えのないアプリやプロセスが起動している

自分でインストールした記憶のないアプリが勝手に増えていたり、タスクマネージャーで見慣れないプロセスが常に動いていたりする場合は注意しましょう。
これは遠隔操作ツール(RAT)や、情報を盗み出すマルウェアが仕込まれている典型的な兆候です。
ハッカーはユーザーに気づかれないようにプログラム名を似せて隠すことが多く、うっかり放置してしまうケースも少なくありません。
少しでも不審なアプリが見つかったら、ネットでその名称を検索し、正規のプログラムかどうかを確認しましょう。
メール送信履歴やSNSログイン履歴に不審な動きがある

自分が送った覚えのないメールが送信されていたり、SNSのログイン履歴に海外など見知らぬ地域からのアクセスがあれば、アカウントが乗っ取られている可能性があります。
すでにハッカーがあなたのパソコンや、アカウントに侵入して操作している恐れが高いでしょう。
放置すると、知らないうちにスパム送信や詐欺行為に悪用される危険もあります。
すぐにパスワードを変更し、二段階認証を設定するなどの対策を取りましょう。
同時に、どの端末からアクセスがあったかを必ずチェックすることが、被害防止につながります。
セキュリティソフトが無効化または警告が出ない状態になっている

セキュリティソフトが突然動作を停止したり、更新ができなくなった場合は危険な兆候です。
ハッカーがウイルス検出を避けるために、セキュリティ機能を意図的に無効化している可能性があります。
特に警告メッセージがまったく表示されなくなった場合、内部で不正な変更が加えられていることがあります。
信頼できる別のセキュリティツールを使って状態を確認するか、オフラインでのスキャンを行いましょう。
インターネットの通信量が異常に増えている

最近パソコンの通信量が異常に増えたと感じる場合は、外部サーバーへのデータ送信が行われているかもしれません。
ハッキング被害では、ユーザーの個人情報やファイルを外部へ送信するプログラムが常駐しているケースがあります。
特に、深夜や使用していない時間帯にも通信が続いている場合は要注意です。
ネットワークモニターツールやルーターの管理画面で通信履歴を確認し、どのアプリが通信しているのかを特定しましょう。
もし不明な通信先があれば、即座にネットワークを遮断し、専門業者に相談することをおすすめします。
PCがハッキングされたか確認するためのチェックポイント

PCのハッキングが疑われる場合は、その真偽を確認する必要があります。
ここでは、PCのハッキングを確認するためのポイントを解説します。
タスクマネージャーで不明なプロセスを確認する方法(Windows)
.png)
Windowsユーザーであれば、タスクマネージャーを開いて現在動作しているプロセスを確認することが有効です。
Ctrl+Shift+Escキーを同時に押すとタスクマネージャーが起動し、「詳細」タブに一覧が表示されます。
ここに見慣れないプロセスや、CPUやメモリを異常に消費しているものがあれば注意が必要です。
特に名前が英数字の羅列や「svchost.exe」に似た偽装プロセスは要警戒してください。
不明な項目を右クリックして「ファイルの場所を開く」を選び、正規のシステムフォルダ以外にある場合は不正プログラムの可能性が高いといえます。
Windowsイベントビューアーで不審なログをチェックする

Windowsのイベントビューアーは、システムの動作履歴を詳細に記録しているツールです。
スタートメニューで「イベントビューアー」と検索し、「Windowsログ」→「セキュリティ」や「システム」を確認します。
もし自分が操作していない時間帯に不明なユーザーのログイン記録やアクセスが残っている場合は、侵入の兆候と考えられます。
また、同じ時間帯にエラーや警告が頻発していると、ハッカーがシステムに変更を加えた可能性もあります。
原因不明のログが続く場合は、セキュリティソフトでスキャンを実施するか、専門家による診断を検討しましょう。
アクティビティモニタでリソース使用状況を確認する(Mac)
.png)
Macを使用している場合は「アクティビティモニタ」を活用すると、システム全体の動作状況を把握できます。
「アプリケーション」→「ユーティリティ」→「アクティビティモニタ」を開くと、CPUやメモリ、ネットワーク使用量が一覧で確認できます。
ハッキングやマルウェアが関与している場合、電力消費が増えたり、ファンが常に動作するなどの症状が出ることもあります。
不審な動作を見つけたときは、そのプロセス名を調べ、Apple公式以外の不明なアプリなら削除や隔離を検討しましょう。
ログイン履歴・アカウントアクセスの確認手順(Microsoft・Google)
.png)
MicrosoftやGoogleアカウントを利用している場合、それぞれのログイン履歴を確認することで不正アクセスを特定できます。
Microsoftアカウントでは「セキュリティ」→「サインインアクティビティ」を開くと、アクセス元の地域やデバイスが表示されます。
Googleの場合も「Googleアカウント」→「セキュリティ」→「デバイスの管理」から確認可能です。
自分が使っていない地域やデバイスからのアクセスがあれば、即座にパスワードを変更しましょう。
二段階認証を設定していない場合は、有効にして次回以降の不正アクセスを防ぎましょう。
ブラウザ拡張機能・アドオンに不審なものがないか確認する

ブラウザの拡張機能(アドオン)は便利な一方で、悪意あるプログラムが紛れ込むこともあります。
見覚えのない拡張機能が追加されている、もしくは検索結果や広告の内容が急に変わったと感じる場合は要注意です。
Chromeなら「設定」→「拡張機能」、Edgeなら「拡張機能の管理」、Safariなら「環境設定」→「機能拡張」から一覧を確認できます。
不明な拡張機能があればすぐに削除し、ブラウザの設定を初期化しておくと安心です。
ウイルスやマルウェア感染の有無を正確に調べる方法

次に、ウイルスやマルウェアに感染していないか、正確に調査する方法を紹介します。
WindowsDefenderを使ってフルスキャンを行う

Windowsを利用している場合、最も基本的で信頼性の高い方法が「WindowsDefender(MicrosoftDefender)」によるフルスキャンです。
スタートメニューから「Windowsセキュリティ」を開き、「ウイルスと脅威の防止」→「スキャンのオプション」→「フルスキャン」を選択します。
フルスキャンは時間がかかりますが、パソコン全体の隅々まで検査でき、潜んでいるウイルスやマルウェアを検出します。
特に知らないファイルやアプリが増えている場合は、早めに実施することで被害を最小限に抑えられます。
スキャン結果に警告が出た場合は、指示に従って隔離または削除を行い、再起動後にもう一度確認すると安心です。
セーフモードでのスキャンで潜伏ウイルスを検出する

通常モードでは削除できないウイルスやマルウェアは、Windowsを「セーフモード」で起動してスキャンを行うと検出しやすくなります。
セーフモードでは不要なプログラムが動作せず、感染ファイルが隠れる余地が少なくなるためです。
起動時に「F8」キーまたは「Shift+再起動」でセーフモードを選び、Defenderや別のセキュリティソフトでスキャンを実行します。
これにより、通常では停止できない悪質なプロセスを隔離または削除できます。
ブラウザハイジャック(検索結果の改ざん)を確認する方法
を確認する方法.png)
検索結果が意図しないサイトに飛ぶ、ホームページが勝手に変わるといった現象は「ブラウザハイジャック」の可能性があります。
これは広告収益や情報窃取を目的とした不正なプログラムによるもので、早急な対処が必要です。
まずブラウザ設定を開き、ホームページや検索エンジンの設定が書き換えられていないか確認しましょう。
さらに、拡張機能の中に不審なものがないかをチェックし、不要なものは削除します。
設定をリセットしても改善しない場合は、マルウェア対策ソフトでのスキャンを行い、完全駆除を目指してください。
信頼できるセキュリティソフトで二重チェックを行う

感染の可能性をより確実に排除するために、複数の信頼性の高いセキュリティソフトを併用することが効果的です。
異なるエンジンでスキャンを行うと、特定のソフトでは見逃されがちな新種マルウェアも発見できることがあります。
ただし、同時に常駐させると動作が重くなったり競合する恐れがあるため、片方を一時停止して使用するのがおすすめです。
ハッキングが疑われた場合に取るべき5つの緊急対処法

PCがハッキングされていると感じたなら、すぐに対応することが大切です。
ここでは、ハッキングの可能性がある場合の緊急対処について解説します。
インターネット接続を一時的に遮断する

ハッキングの疑いが生じたら、まずはPCをインターネットから遮断しましょう。
不正アクセスや情報送信を防ぐには、LANケーブルを抜く、Wi-Fiをオフにするなど、物理的に接続を遮断するのがおすすめです。
ハッカーは被害者が気づかないうちに外部サーバーへデータを送信したり、リモート操作を続けることがあります。
通信を止めることで、それ以上の情報漏えいや遠隔操作を防げます。
重要なパスワードをすべて変更する

ネットワークを遮断したら、次にパスワードを変更します。
この場合、ハッキングされていない別の安全な端末を使用するのがポイントです。
特に、銀行・クレジットカード・メール・SNS・クラウドストレージなど、個人情報や金銭に関わるアカウントを優先して変更します。
できれば、同時に二段階認証の設定も有効にしておくと、再侵入を防ぐ効果が高まります。
セキュリティソフトで駆除・隔離を行う

ネットワーク遮断とパスワード変更が完了したら、感染源の特定と除去を行う段階に入ります。
信頼できるセキュリティソフトを最新の状態に更新し、フルスキャンを実施します。
検出されたウイルスやマルウェアは、指示に従って「削除」または「隔離」を行ってください。
ただし、一部の悪質なマルウェアは、通常スキャンでは削除できないことがあります。
完全な駆除が難しい場合は、専門の調査業者に依頼することを検討しましょう。
銀行口座やクレジット情報の不正利用を確認する

最後に確認すべきなのが、金銭的な被害の有無です。
ハッカーは個人情報だけでなく、金融情報を狙うケースも多くあります。
ネットバンキングのログイン履歴や、クレジットカードの利用明細を必ずチェックしましょう。
もし見覚えのない引き落としや取引履歴があれば、すぐに銀行やカード会社に連絡して利用停止を依頼してください。
今後ハッキングされないためのセキュリティ強化術

ハッキング被害を防ぐには、日常的なセキュリティ意識の向上が欠かせません。
ここでは、PCを安全に保ち、再発を防ぐための実践的な対策を紹介します。
Windows・Macの自動更新を有効にする

基本的かつ効果的な防御策は、OSやソフトウェアを常に最新の状態に保つことです。
WindowsやMacには自動更新機能が備わっており、これを有効にしておけば、脆弱性を悪用されるリスクを大幅に減らせます。
多くのサイバー攻撃は古いシステムを狙って行われるため、更新を後回しにするのは危険です。
特にセキュリティパッチやブラウザの更新通知が出た場合は、すぐに適用する習慣をつけましょう。
強力なパスワードと二段階認証を設定する

強力なパスワードは不正アクセスを防ぐ最初の防壁です。
英数字・記号を組み合わせ、12文字以上の複雑なものに設定しましょう。
また、二段階認証(2FA)を導入すれば、ログイン時に追加の認証コードが必要となり、たとえパスワードが漏洩しても被害を防げます。
不要な共有設定・リモートアクセス機能をオフにする
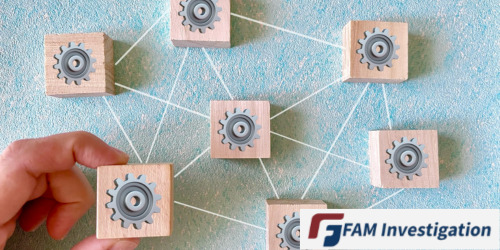
ファイル共有機能やリモートデスクトップは便利ですが、使わない状態で放置しておくと、外部からの侵入口になりかねません。
特に企業ネットワークでは、共有フォルダの権限設定ミスが情報漏えいの原因になることもあります。
使用していない共有設定やリモート接続はすべて無効化、またはアクセス制限を厳重に設定しましょう。
公共Wi-Fi使用時はVPNを活用する

カフェやホテルなどの公共Wi-Fiは便利ですが、暗号化が不十分な場合、ログイン情報やクレジットカード番号が盗まれるケースがあります。
公共Wi-Fiを安全に利用するためには、通信を暗号化できるVPN(仮想専用ネットワーク)を導入するのが効果的です。
VPNを通すことで、第三者が通信内容を傍受しても解読できなくなるためです。
外出先で業務やオンライン決済を行う際には、VPN接続を必ず有効にしましょう。
不審なメール・リンクを開かないための基本ルール

ハッキングの多くは、フィッシングメールや偽サイトへの誘導から始まります。
送信元が不明なメールの添付ファイルやリンクは、絶対に開かないようにしましょう。
たとえ知人や有名企業を装っていても、文面に不自然な点があれば要注意です。
リンクをクリックする前にURLを確認し、「https://」から始まっているかをチェックします。
自力で解決できないときは専門業者へ相談を

ハッキングの被害が深刻な場合や、自分では原因を特定できない場合は、専門家のサポートを受けることが重要です。
ここでは、相談すべき状況や、信頼できる専門業者を選ぶ際のポイントを解説します。
個人情報流出や金銭被害の兆候がある場合はすぐに対応を

もし、クレジットカードの不正利用や、SNS・メールアカウントの乗っ取りが発覚した場合は、すぐに関連機関へ連絡してください。
カード会社や銀行では、不正利用に関する補償制度が設けられていることが多く、迅速に報告すれば被害を最小限に抑えられます。
また、SNSやクラウドサービスの場合も、サポート窓口に被害報告を行うことで、アカウントの一時停止や復旧措置を受けられることがあります。
対応を怠ると被害が拡大することがあるため、早期行動が重要です。
業者選びのポイント

ハッキング被害に対応する業者を選ぶ際は、信頼性と実績を重視しましょう。
公式サイトに実際の調査事例や対応実績が明記されているかを確認し、料金体系が明確な会社を選ぶのが基本です。
事前に見積もりを取り、対応範囲・費用・期間などを丁寧に説明してくれる業者を選びましょう。
口コミや評判を確認し、実在するオフィスがあるかどうかもチェックしておくと安心です。
専門調査会社を利用する際の注意点

専門調査会社に依頼する場合は、契約内容を必ず書面で確認し、トラブル防止のために不明点をそのままにしないことが大切です。
調査範囲や報告方法、費用の内訳、追加料金の有無などを事前に明確にしておきましょう。
また、調査の過程で個人情報を共有する場合もあるため、守秘義務が徹底されている会社を選ぶことが重要です。
信頼できる専門会社に依頼すれば、的確な原因特定と再発防止策を受けられるでしょう。
再発防止のための定期的なセキュリティ診断のすすめ

ハッキング被害の再発を防ぐには、定期的なセキュリティ診断が効果的です。
専門業者による診断では、システムの脆弱性や不正アクセスの痕跡を詳しく調べることができます。
特に企業や個人事業主は、年に1回程度の診断を実施することで、潜在的なリスクを早期に発見できるでしょう。
診断結果に基づいてOS更新やパスワード管理の見直しを行うなど、問題が起きないように備える意識を持つことが重要です。
PCがハッキングされたか調べて安全な環境を整えましょう

PCのハッキング被害は、放置すると個人情報の流出や金銭的損失に発展する恐れがあります。
不審な動作やアクセス履歴に気づいたら、早めの調査と対処が何より大切です。
ただし、自力での確認に限界を感じた場合は、専門知識を持つ法人興信所にご相談ください。
状況の分析から原因特定、再発防止までをトータルでサポートいたします。
一人で悩まず、安心してネットを使える環境を一緒に取り戻しましょう。
ご相談とご依頼までの流れ
-
まずはフリーダイヤル・お問い合わせメールフォーム・LINEよりお問い合わせ下さい。問題の概要や状況をお聞き致します。
-
無料面談にて、電話やメール、LINEにて無料相談頂いた内容の詳細をお聞きし、お手伝い出来る調査やサポートをご提案致します。その際、お見積りをご提示致します。
お見積り内容には、調査期間・調査員数・調査方法・調査報告書の作成費などが含まれています。 -
お見積り金額・調査内容に十分ご納得頂けた場合、委任契約のお手続きに入ります。下記書面に署名捺印をして頂き、契約完了となります。書面には、調査目的・期間・費用の詳細・調査結果の報告方法・個人情報の取り扱いなどが記載されています。
-
契約書面を基に予備調査、本調査の順に調査を実施します。その際、随時途中経過をご報告致します。追加調査が必要な場合は、都度ご相談下さい。
-
全ての調査終了後、書面もしくはデータにて調査報告書を提出致します。必要に応じて各種専門家のご紹介やアドバイスなどのアフターサービスも行なっております。
お問い合わせ
ご相談は、プライバシー 秘密事項厳守で承ります。
クレジット決済のご案内
お支払い方法について、銀行振込のほか、各種クレジットカードにも対応しております。
ご都合のよい方法をお選びいただけます。
クレジットカード決済は、テレコムクレジット株式会社にて、おこなっております。
※ ご利用者様のクレジットカードの内容はSSLにて厳重に保護されます。
※ 提供サービスの特性上、決済後の返金はお受け出来かねます。