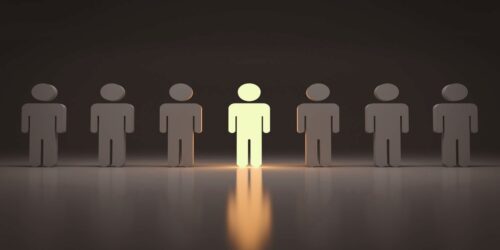調査ファイル
リベンジ退職を対策するには?企業が確認すべき事例も解説


読み終わるまで 8 分
「リベンジ退職に企業はどのように対策するべき?」
「事前にどんな予防をしておけばいい?
近年、リベンジ退職が話題に上がることが多く、企業側はさまざまな予防・対策が求められます。
とはいえ「リベンジ対策」と一言でいってもさまざまな形があり、事例も多岐にわたります。
そのため、予防や対策方法に悩んでいる経営者・担当者は少なくないでしょう。
そこで本記事では、リベンジ退職の対策方法、事例について詳しく解説していきます。
目次
リベンジ退職とは?
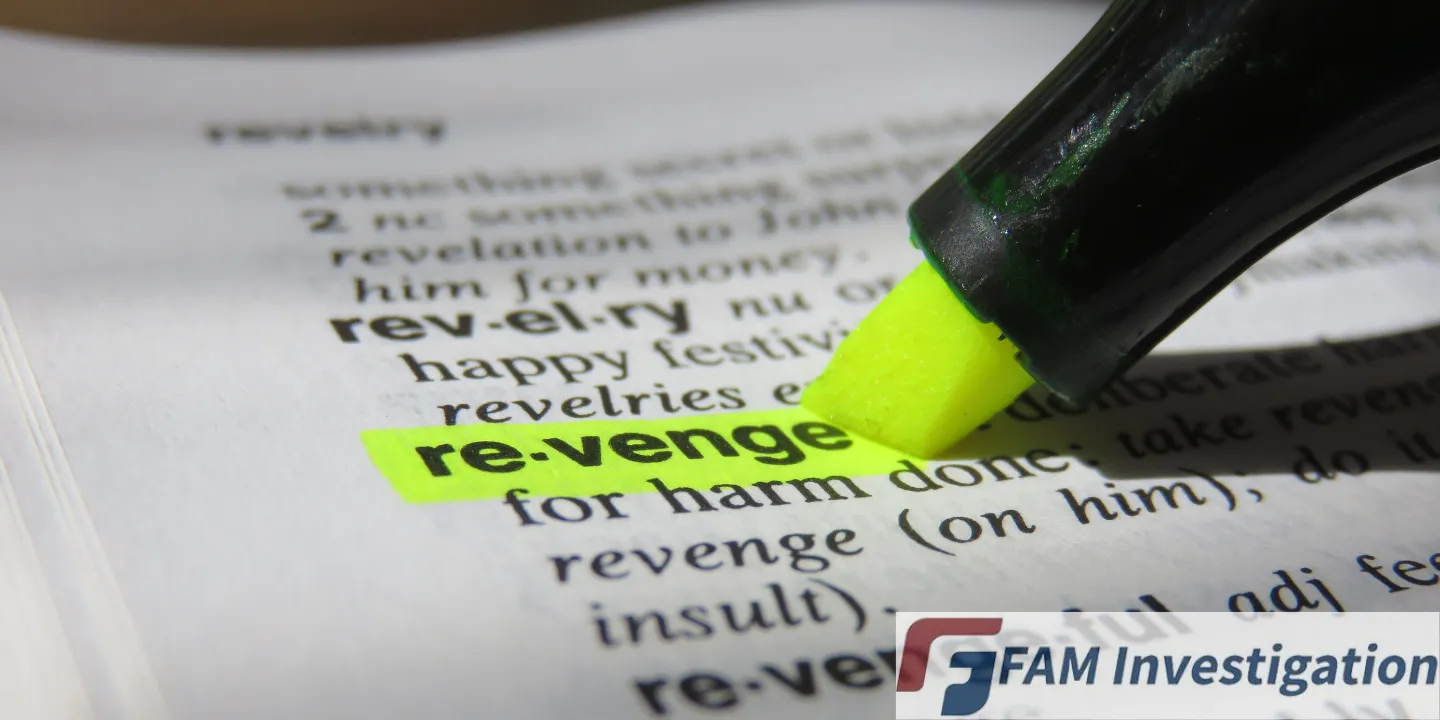
リベンジ退職とは、退職する従業員が会社に対して意図的に不利益を与える行動をとることを指します。
行動の例としては、重要データの削除、顧客情報の持ち出し、引継ぎ拒否、SNSへの内部情報の投稿などが挙げられます。
こうした行動の背景には、職場環境や人間関係に対する不満、評価への不服などがある場合が多いです。
表面上は通常の退職に見えても、実際には業務妨害や報復的意図が含まれているケースもあります。
被害を防ぐためには、こうしたリスクの存在を社内で明確に認識し、事前の対策が重要です。
リベンジ退職によって発生する損害

データの削除・破壊

退職直前に業務データを削除または破壊するケースがあります。
対象は、社内の共有ドライブ、クラウドストレージ、業務用端末のファイルなど多岐にわたります。
突然のデータ消失は、業務の遅延や取引先とのトラブルにつながりかねません。
データ消失が発覚した場合は、削除時刻と対象ファイルを確認し、ログを保全したうえで復旧作業を行いましょう。
引継ぎ拒否・虚偽報告

退職前に引継ぎ拒否をしたり、虚偽報告をしたりすることで、損害につながります。
後任者が業務を正しく把握できず、対応の遅れやトラブルが発生してしまいます。
引継ぎの場では、書面とデジタル両方で記録を残し、第三者でも内容を理解できる状態にしておくことが重要です。
SNSで内部情報拡散

退職者が企業内部の情報をSNSに投稿し、拡散されるケースもリベンジ退職の一種です。
内容はさまざまですが「上司のパワハラ」「不適切な経営方針」「劣悪な職場環境」などが投稿される傾向にあります。
投稿内容によってはいわゆる「炎上」に発展し、企業のイメージが大きく損なわれることもあります。
たとえ真っ当な企業であっても、投稿の広まり方によってはネガティブな印象を与えかねません。
そのため、未然に防ぐことが重要です。
リベンジ退職の事例
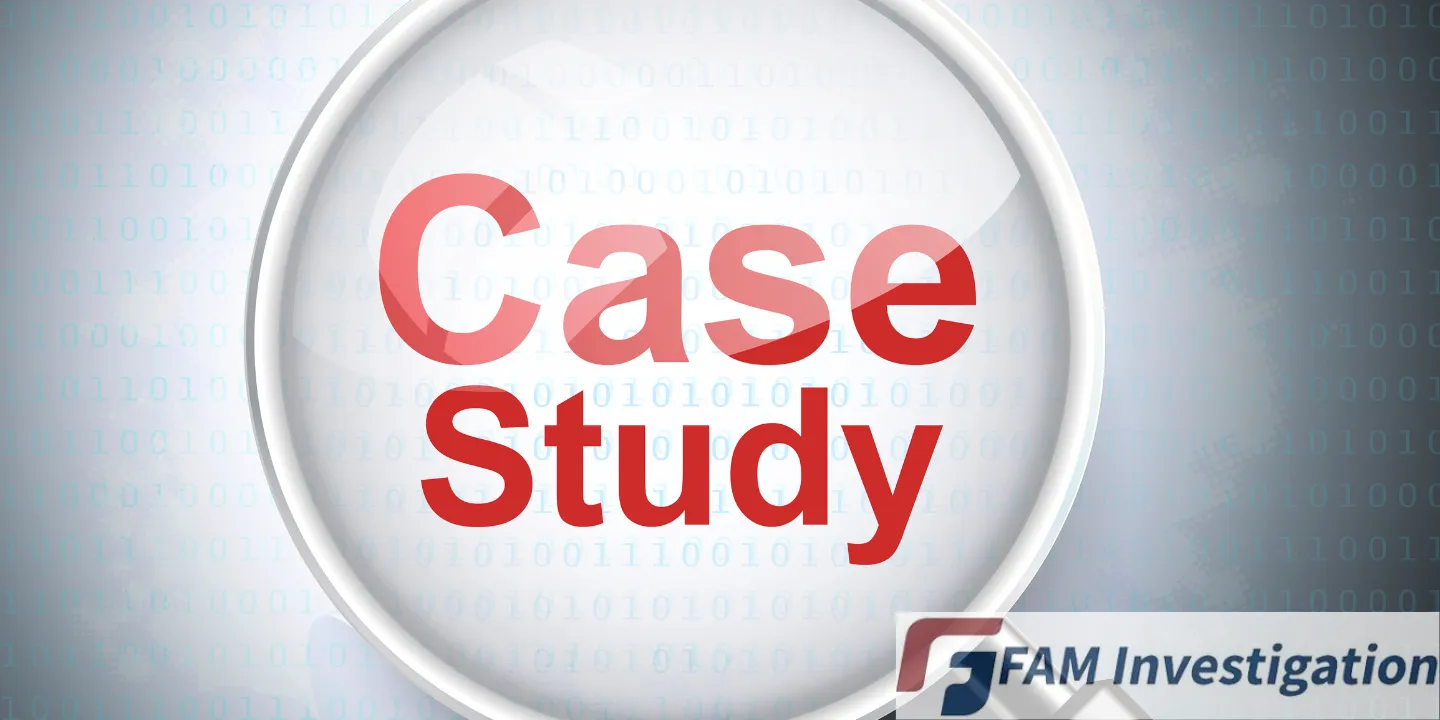
リベンジ退職の主な事例をまとめました。
事例を踏まえ、損害と対策を具体化して今後の方針を検討しましょう。
顧客名簿を競合へ持ち出し

退職者が、在職中に社内の顧客名簿を私的にコピーし、転職先の競合企業で使用した事例があります。
営業先や担当者、契約履歴などが持ち出され、転職後にその情報をもとに営業が行われていました。
企業側は秘密保持契約の違反として法的措置を取りましたが、裁判では「情報の秘密管理が不十分」と判断され、請求が棄却されたケースもあります。
結果として、顧客の一部が競合に流出し、売上の減少や信頼の低下につながっています。
共有ドライブのデータを大量削除

退職者が会社の共有ドライブ内に保存された業務データを、退職直前に意図的に削除した事例があります。
削除されたのは技術資料・業務手順書・顧客対応履歴などです。
最終的にはデータの復旧はできたものの、作業には多くの人員と時間が必要となりました。
企業側は不法行為による損害賠償を求めて提訴し、裁判では元従業員に対して損害賠償の支払いが命じられています。
このケースでは、行為者が元従業員であることが分かったため損害賠償請求ができたものの、証拠がないと不可能です。
そのため、このようなトラブルが発生したときに、行為者を特定できる環境にしておくことが重要です。
引継ぎを拒否し手順・パスワードを秘匿

退職者が業務の引継ぎを拒み、関係するアカウントのパスワードや手順書を社内に一切渡さなかった事例も見られます。
このケースでは、担当者しか把握していなかったファイルの管理権限や顧客対応フローが共有されておらず、業務の再開に数週間を要しました。
業務の属人化や口頭引継ぎが原因となっており、企業側の管理体制にも課題があったとされています。
SNSで内部情報を公開・誹謗投稿し炎上

退職後に元従業員がX(旧Twitter)に、社内の内部事情や特定の上司への不満を書き込んだケースもあります。
これによってパワハラが発覚して炎上し、企業イメージが大きく低下しました。
退職者の大きな不満によってもたらされているため、普段から会社内でパワハラがないか、従業員に不満が生まれていないかヒアリングが大事です。
リベンジ退職の対策を段階別に解説
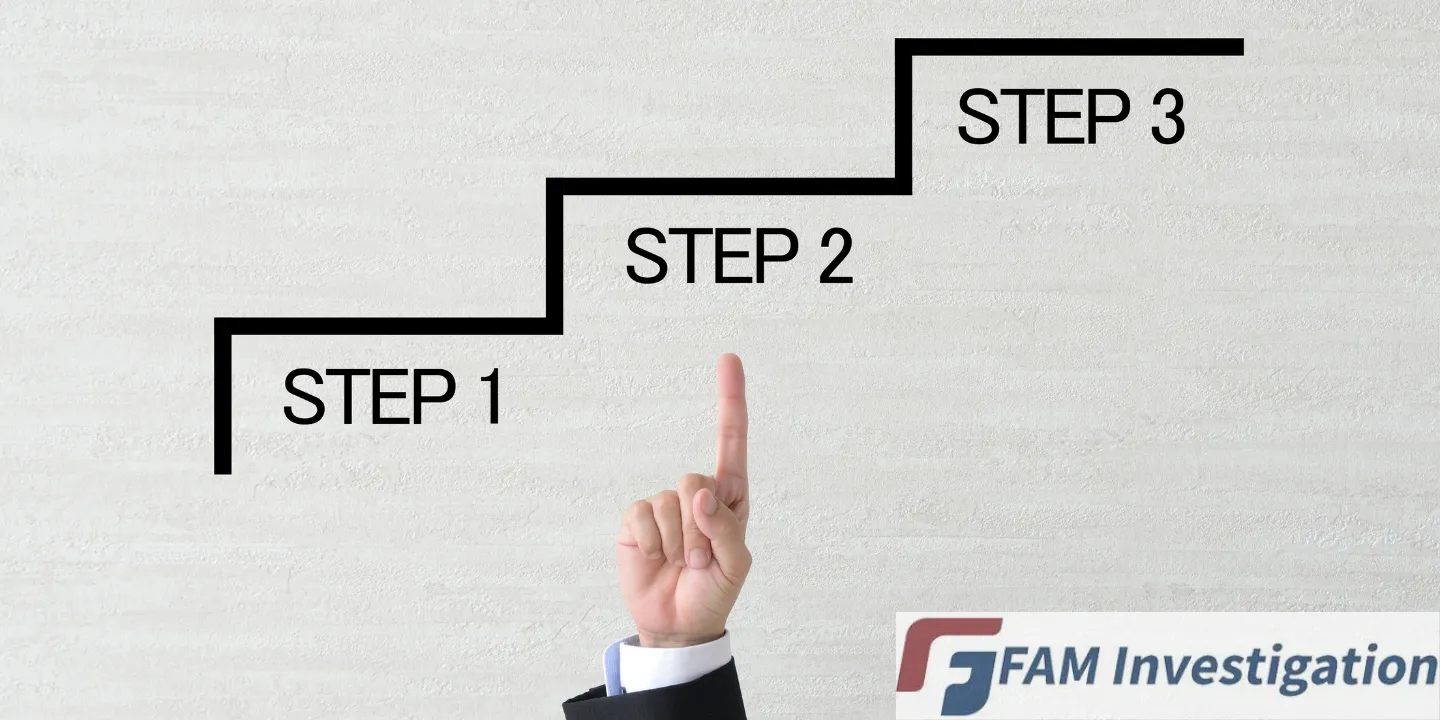
リベンジ退職の対策は「平時」「退職前」「退職後」の3つの段階ごとにやるべきことが異なります。
各段階の対策を確認しておきましょう。
リベンジ退職の予防策
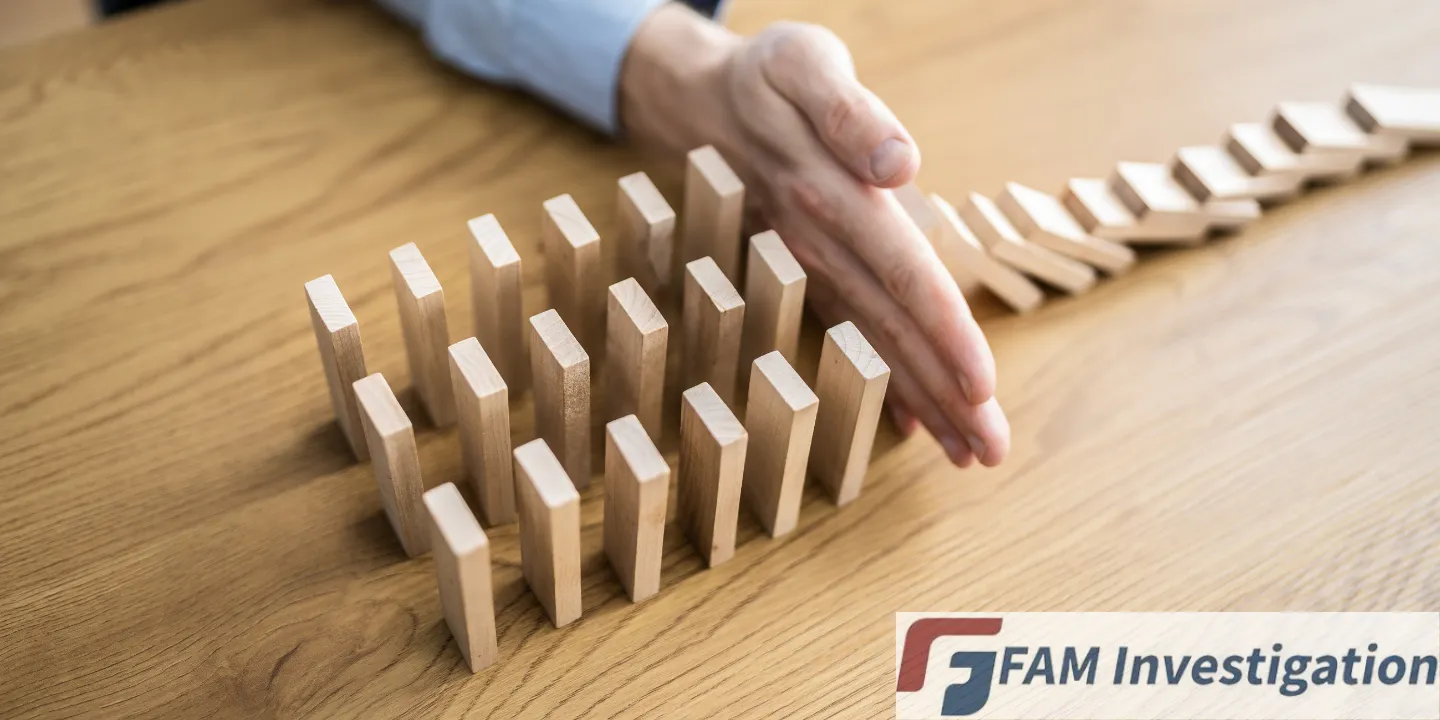
リベンジ退職の予防策は以下の通りです。
- 就業規則・退職手続規程・秘密保持条項の整備
- 業務マニュアルや引継ぎテンプレートの標準化
- アカウント・権限見直しの定期実施
- 操作ログ・アクセス履歴の記録と保管
- 社用データの私物端末への保存・転送の制限
- 社内アンケートや面談による不満の早期把握
上記の通り、リベンジ退職の予防策は、制度と運用の両面から準備が重要です。
就業規則や退職手続規程では、秘密保持義務・データ返却義務などを明記し、従業員が正しく理解できる状態にしておきましょう。
情報システム面では、不要な管理権限の付与を避け、ログや履歴を残す運用体制を日常的に整備しておく必要があります。
定期的なアカウントや権限の見直し、教育によって、制度の形骸化を防ぎ、社内全体でのリスク意識の共有ができます。
そもそも、リベンジ退職というのは「退職時に会社に対して意図的に不利益を与える行動」なので、従業員は会社に対して何らかの不満を持っている可能性が高いです。
そのため、従業員の不満やストレスに早期に気づくため、定期的な面談・社内アンケート・外部窓口の設置など、声を拾う体制を整えておくことも大事です。
従業員の不満を解消し、退職するにしても円満な状態にできれば、根本からリベンジ退職を避けられるでしょう。
退職から最終出社までの対策・予防
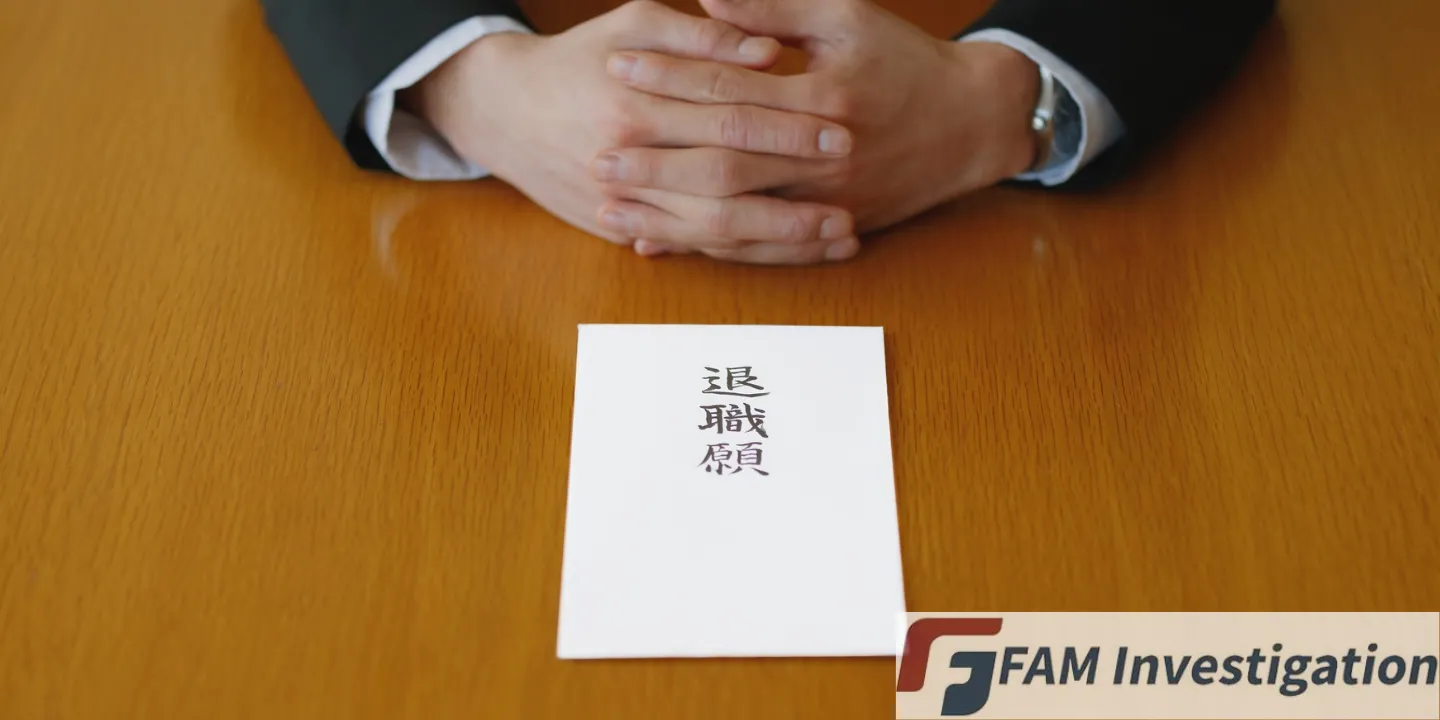
最終出社するまでにしておきたい対策・予防は以下の通りです。
- アカウント停止の段階的スケジュール設定
- 社用PC・スマホ・カード・資料等の物品リストアップと返却管理
- 引継ぎ資料の提出・確認・保管
- 誓約書(守秘義務・返還義務など)の再確認と署名取得
- 退職理由・不満点を把握する退職面談の実施
退職の意思が伝えられてから最終出社日までの期間は、情報流出のリスクが最も高まるタイミングです。
この間に行うべき対応は、感情的な対応ではなく、あらかじめ決められた手順に沿って確実に処理することが求められます。
まずは、退職日程や引継ぎ期限、物品返却日などを明文化し、当人とすり合わせておきましょう。
情報システム系のアカウントは、業務に支障が出ない範囲で段階的に権限を制限し、最終出社日の時点で一括停止できるよう計画的に進めるのも一つの手です。
引継ぎ内容については、資料提出だけでなく第三者(上司や担当者)が内容を確認するプロセスを必ず入れましょう。
未然にトラブルを防ぐ観点から、退職理由や不満を把握する面談の実施も有効です。
退職後の対策・対応

退職後にしておきたい対策・対応は以下の通りです。
- 削除・持ち出しなどの不審操作の有無をログで確認
- データ復旧やアクセス履歴の証拠保全
- SNS投稿・口コミなどの外部情報の監視と記録
- 契約違反や損害発生時の法的対応
- 必要に応じて外部調査機関・弁護士と連携
- トラブルの原因分析と社内ルールの見直し
予防としてできるのは退職前までで、リベンジ退職が発覚した場合は、早期に対処をして今後の対応を考える必要が出てきます。
データの削除・持ち出しなどがあった場合はログを確認し、データ復旧や証拠の保全に努めましょう。
SNSや口コミサイトでの投稿が見つかった場合は、スクリーンショットやURLの記録を残し、内容によっては削除請求や名誉毀損対応を検討します。
また、契約違反や実害が確認できた場合は、損害賠償の請求も視野に入ります。
状況によっては、探偵のような調査機関や弁護士と連携した対応を検討しましょう。
再発防止のため、原因の振り返りとルールの見直しを行い、社内共有・教育することも大事です。
探偵ならリベンジ退職の対策が可能
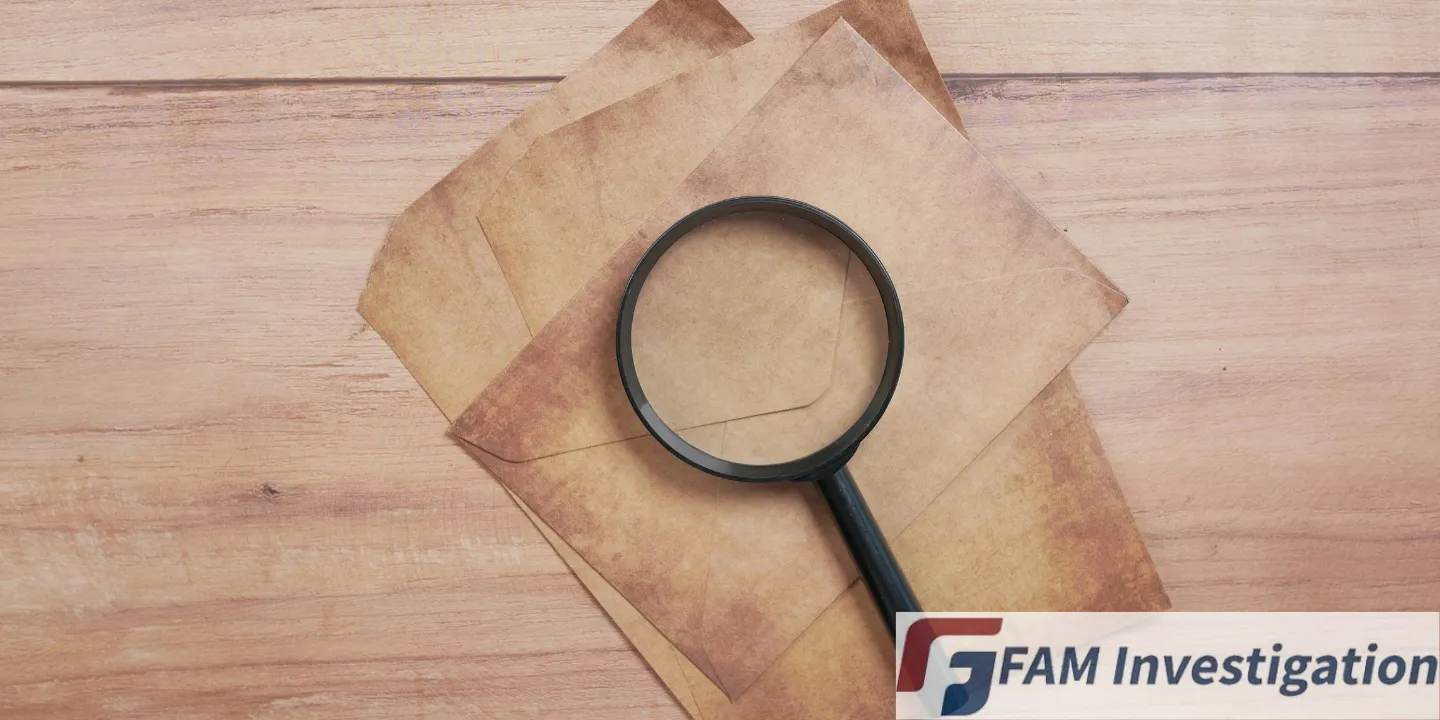
前述したように、リベンジ退職が発覚した場合は、探偵や弁護士などと連携して対応を進めていくことになります。
探偵は以下のようにさまざまな対策ができるので、リベンジ退職発覚時にはまず探偵に相談することをおすすめします。
- 顧客名簿の持ち出しや流出の調査
- SNSの書き込みから相手を特定
- データ削除や情報破壊の痕跡を証拠として残せる
- 引継ぎ拒否や隠ぺいされた業務情報の有無を確認
- トラブルが表面化する前段階からの対策
- 調査報告書を社内対応や法的手続きに活用
- 弁護士の紹介
それぞれ解説していきます。
顧客名簿の持ち出しや流出の調査

これまで紹介したように、リベンジ退職では退職者が顧客名簿を無断で持ち出し、転職先や個人利用に転用するケースは少なくありません。
そのまま競合に情報が流れた場合、自社の顧客が離れ、信頼を損なう被害が発生する可能性があります。
探偵は、データがどこに流出したか、実際に使用された形跡があるかを、聞き取り調査や外部情報の収集などを通じて確認できます。
必要に応じて、競合先での使用実態の調査をし、損害賠償請求に必要な材料・証拠を揃えることも可能です。
事実関係が曖昧で動けないという場合でも、まずは探偵による調査で状況を整理することは重要です。
SNSの書き込みから相手を特定
![]()
退職者が元勤務先が炎上することを狙って、SNSに社内情報を暴露するケースは近年特に増えています。
探偵は、SNS上の投稿内容やタイミングなどを手がかりに、投稿者の特定ができます。
また、拡散状況の記録、スクリーンショットの取得など、今後の損害賠償請求を想定した証拠保全も可能です。
データ削除や情報破壊の痕跡を証拠として残せる
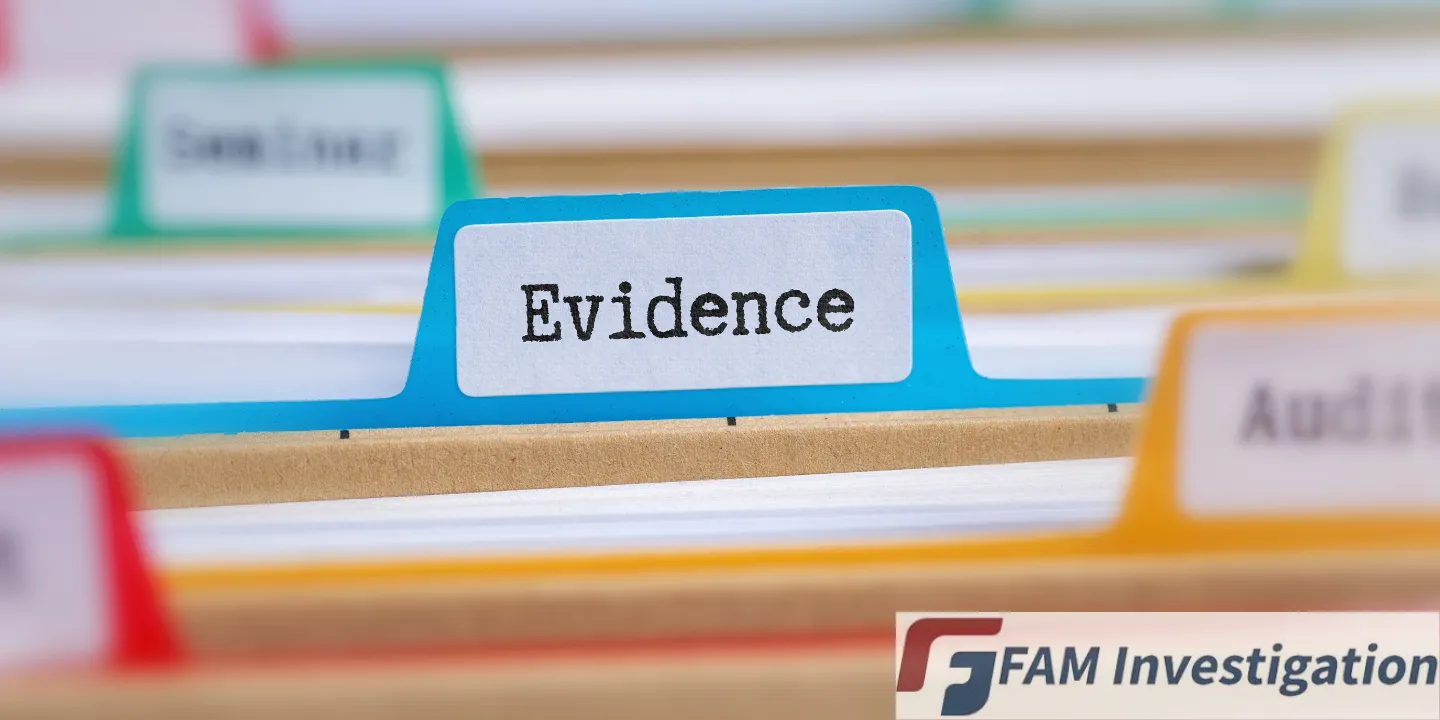
リベンジ退職では、共有フォルダや端末内のファイルを意図的に削除・改ざんするケースがあります。
探偵は、削除操作のタイミングや操作履歴、アクセス権限の状態などを整理し、削除行為の有無を証拠として残せます。
本証拠は、組織内での透明性確保と適切な法的対応を可能にするものです。
そのため、信頼回復と社内制度の再構築において重要です。
リベンジ退職によってデータ削除が発生した場合は、速やかに探偵に依頼し証拠として残せるものがないか確認してもらいましょう。
引継ぎ拒否や隠ぺいされた業務情報の有無を確認

探偵は、引継ぎの実態や隠ぺいされた業務内容の有無を第三者の立場から調査が可能です。
社内のやり取りや資料の記録をもとに、どの情報が共有され、どれが意図的に抜けていたのかを整理します。
そのため、退職者が業務の引継ぎを拒否したり、必要な手順やパスワードを意図的に共有しなかったりしても、よりスムーズな解決を目指せます。
トラブルが表面化する前段階からの対策
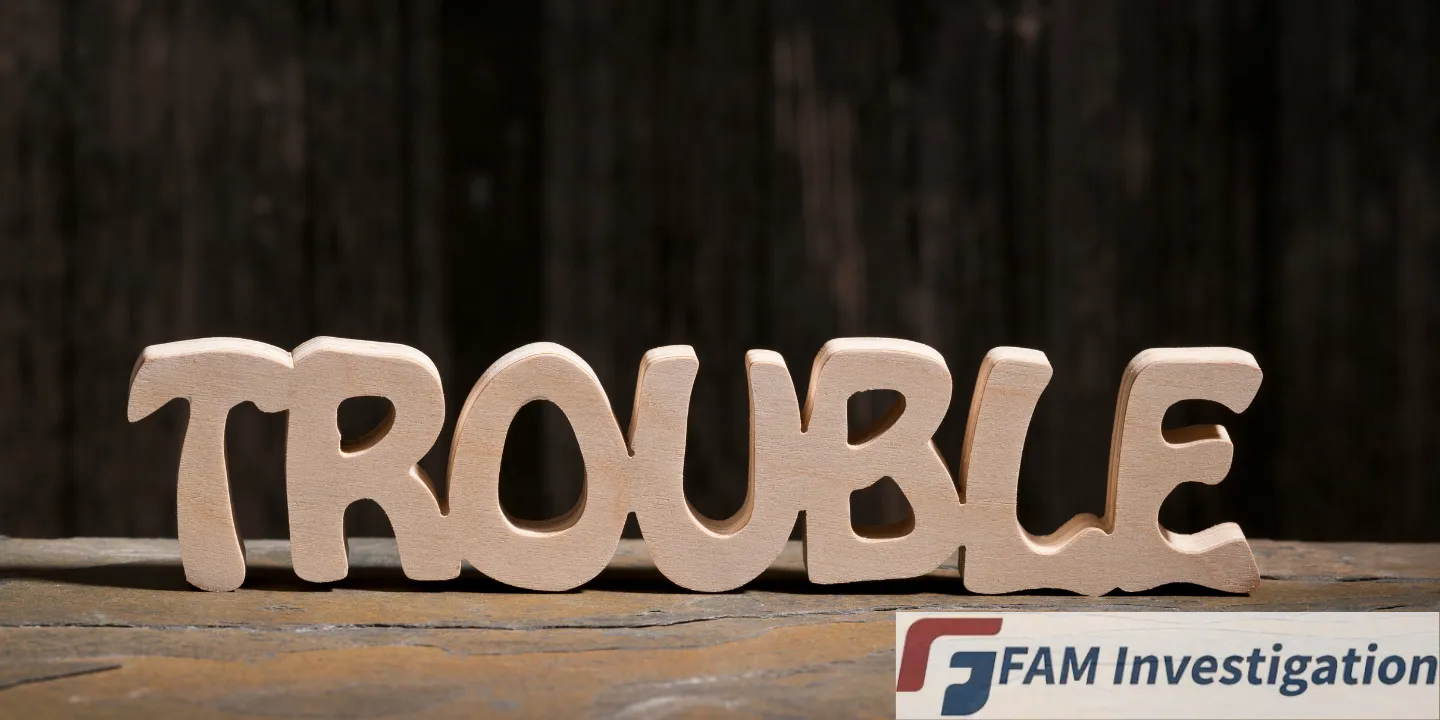
リベンジ退職は、発覚した時点ですでに何らかの被害が生じていることが多く、早期対応が重要です。
探偵は「データの動きが不自然」「従業員の行動に違和感がある」といった段階から、事実関係の確認や証拠整理ができます。
具体的には、アクセスログの操作傾向や、社内外での発言履歴、SNSアカウントの動きなどから、内部で起きている兆候を把握する支援が可能です。
まだ問題が顕在化していない段階であっても、外部の視点で情報を整理することで、対応の判断材料を得られます。
企業側の対応が遅れることで被害が拡大するケースもあるため、予兆段階での事実確認は大いにリスク回避につながるでしょう。
「不安はあるが決定的な根拠がない」と感じた場合でも、探偵へ相談してみるのは一つの手です。
調査報告書を社内対応や法的手続きに活用

調査結果は、報告書として文書化され、社内判断や法的対応の根拠として活用可能です。
報告書には、調査の目的・方法・経過・結果が時系列で整理され、損害賠償請求をする際でも法的に有効な証拠としてまとめられます。
社内では、再発防止策の検討や就業規則の見直しのために使えるため、損害賠償請求を考えていない場合でも調査報告書は大きな役割を持ちます。
さらに、調査報告書は感情や主観ではなく客観的な事実として説明できる資料となるため、社外での説明責任にも有効です。
不明確な状況を整理し、組織としての次の行動を決めるための土台として活用しましょう。
弁護士の紹介

探偵を利用すると、法的対応が必要な状況でも信頼できる弁護士を紹介できます。
リベンジ退職で頻出する法分野に精通した法律事務所と提携している探偵事務所であれば、証拠収集段階から法律対応までスムーズに連携可能です。
自社でゼロから弁護士を探す場合、専門性・過去事例の確認・信頼関係の構築に時間と手間がかかります。
その点、探偵による紹介があれば、リベンジ退職に対応可能な弁護士に直接つながるので、初動の遅れを防げます。
リベンジ退職対策を探偵に依頼する流れ

リベンジ退職の対策を探偵に依頼するなら、今後のおおまかな流れについても理解しておきましょう。
今後の流れをイメージしたうえで、スムーズに対策を進めていきましょう。
1.状況を整理したうえで探偵の無料相談を利用する

まずは、社内で起きている・または疑われているリベンジ退職の状況を整理し、探偵事務所の無料相談を活用しましょう。
以下の情報をまとめておくと相談はスムーズに進められます。
- トラブルの内容
- 退職者の行動履歴
- 削除されたファイル
- SNS投稿の有無
探偵側では、ヒアリングをもとに「調査が必要かどうか」「どの範囲を優先すべきか」といった判断を行い、初動の方針を提案します。
なお、この時点では証拠が揃っていなくても問題はありません。
社内対応に限界を感じた時点で、できるだけ早く探偵の視点を取り入れることがリスクを抑える第一歩になります。
2.調査プランを提示してもらう

初回相談の内容をもとに、探偵から調査プランの提案が行われます。
プランや費用は、調査の目的・調査手法・対象範囲・実施期間・納品物の形式など、案件に応じて個別に設計されます。
同時に、調査開始のための契約・スケジュールなども明確に説明されます。
「いつまでに調査結果が必要か」「どこまで調べてほしいか」といった要望がある場合は、この時点でしっかり共有しておきましょう。
3.調査を実施する
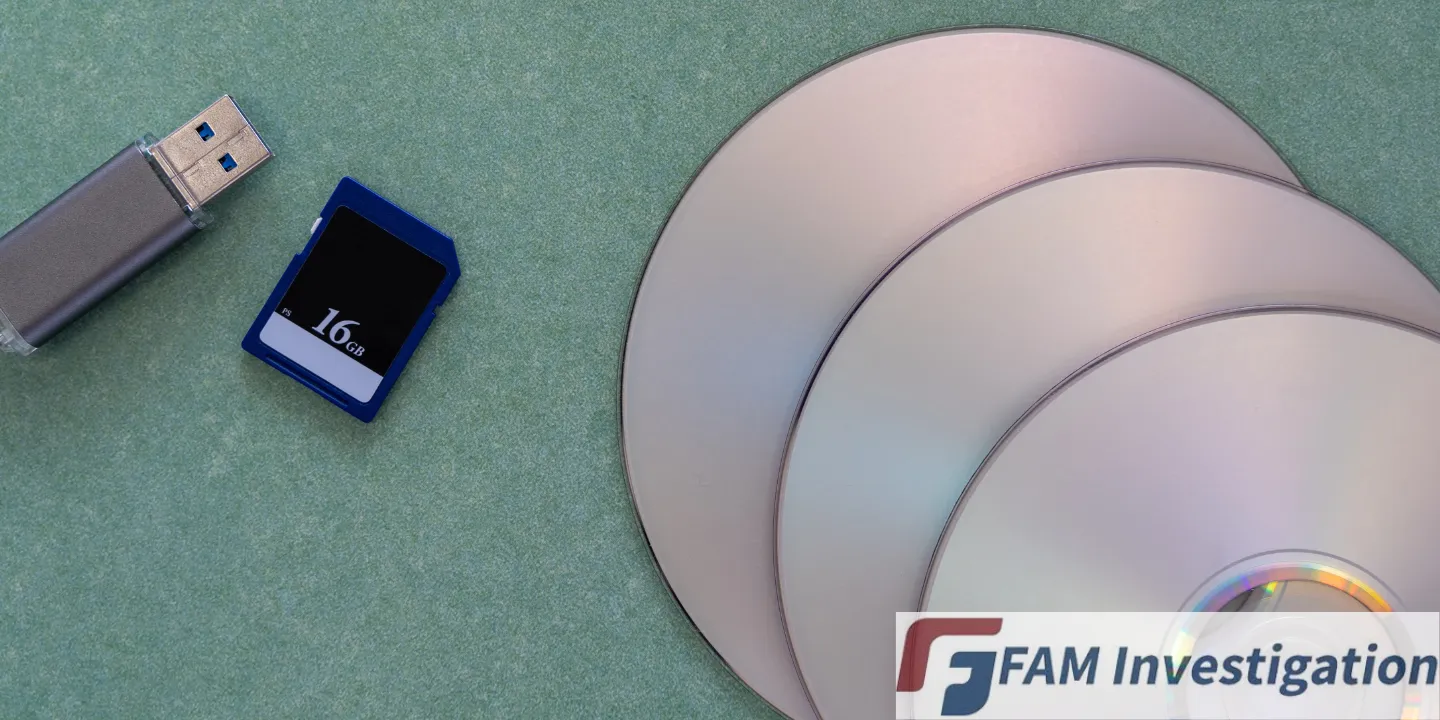
契約後は、合意した調査プランに基づいて、探偵による調査が始まります。
調査内容は事前に相談したプランに基づいて、SNSや外部サービスの確認、関係者への聞き取り、社内の操作履歴やデータの整理などさまざまです。
なお、調査中に新たな事実が判明した場合は、状況に応じて対象範囲の追加や方針の見直しが行われることもあります。
企業側は、進捗報告を通じて調査の方向性を確認しながら、必要に応じた調整を随時相談できます。
4.調査資料の納品と活用

調査が完了すると、探偵から調査報告書や証拠資料が正式に納品されます。
企業側はこの報告書をもとに、社内での懲戒判断や再発防止策の検討、関係者への説明などに活用できます。
事実に基づいた対応を進めるためにも、報告書は単なる調査結果ではなく、次の行動につなげる資料として活用しましょう。
5.必要に応じて弁護士へ依頼

損害賠償請求のような法的対応が必要な場合は、弁護士へ依頼しましょう。
探偵が弁護士と連携している場合は、探偵に相談してください。
探偵経由で弁護士に依頼すれば、証拠の受け渡しから対応開始までがスムーズです。
また、企業側で一から弁護士を探す手間が省け、事案の引継ぎも短時間で完了します。
弁護士は、調査報告書をもとに法的リスクの整理や請求内容の検討を行い、必要に応じて交渉や訴訟を代理します。
社内対応だけでは解決が難しいと判断された場合は、早期に法的措置を視野に入れることが重要です。
リベンジ退職の対策に関するよくある質問
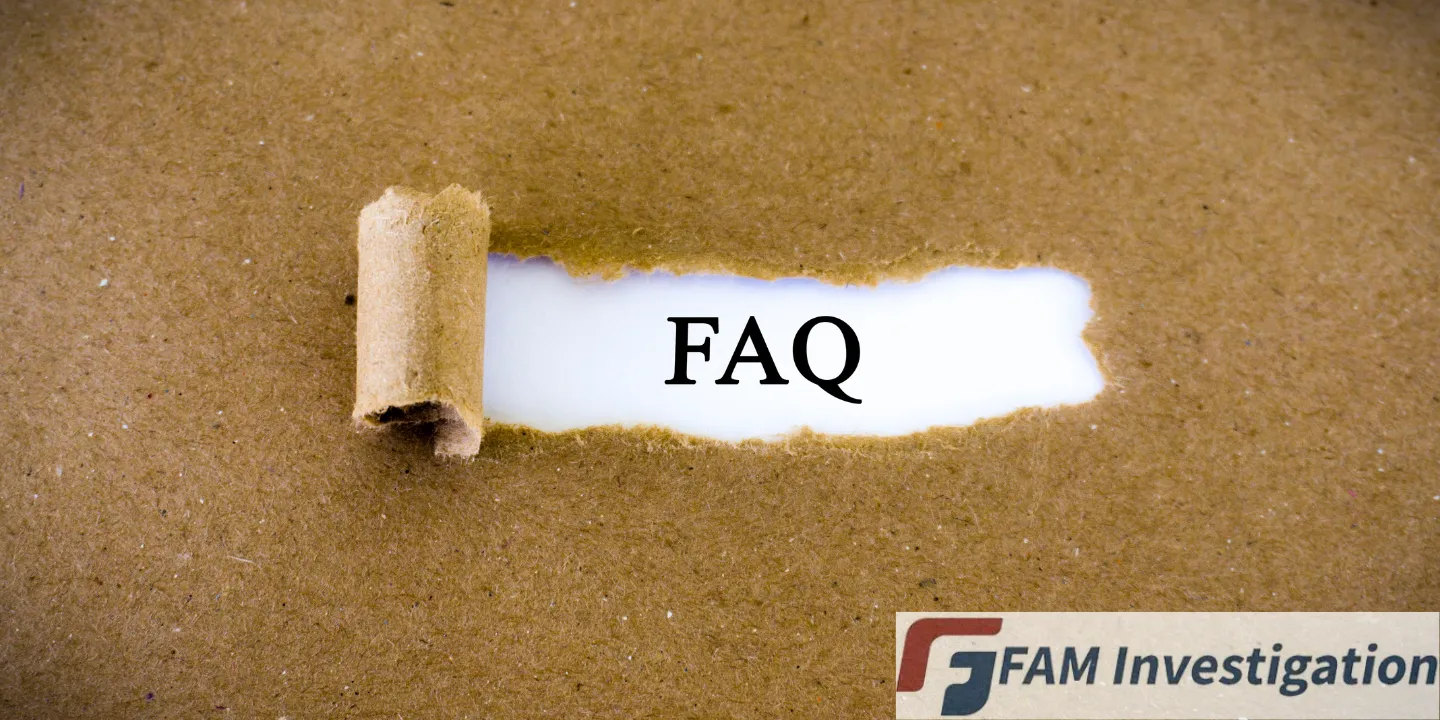
業務を妨害した時点で違法行為と判断される可能性があります。内容を特定し、証拠を確保したうえで対応を検討しましょう。
実害と証拠があれば請求できます。情報漏えいや業務停止による損害が立証できるかが重要です。
調査内容に応じて10万円〜100万円程度かかります。
対象範囲や日数により大きく変動するため事前見積もりが必要です。
まずは事実を整理することが重要です。
情報漏洩やデータ削除などの事実があるのか、会社に実害が出ているのかなど、事実を確認しましょう。
原因や責任の所在は調査を通じて客観的に判断されます。
雇用形態に関係なく発生する可能性があります。
情報へのアクセスや業務の属人化があれば同様のリスクがあります。
そのため、アルバイトやパートに対しても、事前の対策・予防をしておくべきです。
リベンジ退職の対策は法人興信所にお任せください

リベンジ退職によるデータ削除や情報流出などのリスクは、社内だけでは対応しきれない場合があります。
法人興信所所では、リベンジ退職のような法人向けの調査にも対応しており、情報整理から証拠の保全、必要に応じた弁護士連携まで一貫して支援可能です。
「何が起きているのか分からない」「社内だけで対応すべきか判断できない」そんなときこそ、探偵による第三者の視点を入れることが解決への近道となります。
プライバシー・秘密事項厳守で承りますので、まずは無料相談をご利用ください。
ご相談とご依頼までの流れ
-
まずはフリーダイヤル・お問い合わせメールフォーム・LINEよりお問い合わせ下さい。問題の概要や状況をお聞き致します。
-
無料面談にて、電話やメール、LINEにて無料相談頂いた内容の詳細をお聞きし、お手伝い出来る調査やサポートをご提案致します。その際、お見積りをご提示致します。
お見積り内容には、調査期間・調査員数・調査方法・調査報告書の作成費などが含まれています。 -
お見積り金額・調査内容に十分ご納得頂けた場合、委任契約のお手続きに入ります。下記書面に署名捺印をして頂き、契約完了となります。書面には、調査目的・期間・費用の詳細・調査結果の報告方法・個人情報の取り扱いなどが記載されています。
-
契約書面を基に予備調査、本調査の順に調査を実施します。その際、随時途中経過をご報告致します。追加調査が必要な場合は、都度ご相談下さい。
-
全ての調査終了後、書面もしくはデータにて調査報告書を提出致します。必要に応じて各種専門家のご紹介やアドバイスなどのアフターサービスも行なっております。
お問い合わせ
ご相談は、プライバシー 秘密事項厳守で承ります。
クレジット決済のご案内
お支払い方法について、銀行振込のほか、各種クレジットカードにも対応しております。
ご都合のよい方法をお選びいただけます。
クレジットカード決済は、テレコムクレジット株式会社にて、おこなっております。
※ ご利用者様のクレジットカードの内容はSSLにて厳重に保護されます。
※ 提供サービスの特性上、決済後の返金はお受け出来かねます。