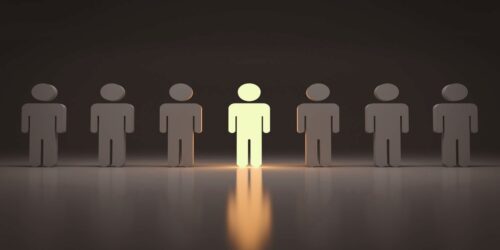調査ファイル
不正の三要素(トライアングル)とは?対策や具体例などわかりやすく解説


読み終わるまで 6 分
企業にとって、不正対策は経営を続けていくうえで欠かせません。
不正が発生すれば、金銭的な損失だけでなく、取引先や顧客からの信頼を失い、再建までに長い時間とコストを要します。
企業内での不正を防ぐためには、人がどのような心理・状況で不正に至るのかを理解することが重要です。
その鍵となるのが「不正の三要素」と呼ばれる理論です。
不正の三要素とは、人間が不正行為に至るまでの「機会」「動機」「正当化」の三つの条件を指します。
これら三つがそろうと不正が起こりやすく、逆に一つでも欠ければ、不正を未然に防ぐことが可能です。
本記事では、不正の三要素について、対策や具体例などをわかりやすく解説していきます。
ぜひ参考にしていただき、従業員の不正を防止し、企業の安定を目指しましょう。
目次
不正の三要素(トライアングル)とは?

不正の三要素(トライアングル)は、企業や組織で起こる不正を理解するうえで欠かせない考え方です。
不正の三要素が持つ意味や背景を整理し、実務にどう活かせるのか詳しく見ていきましょう。
人間が不正行為に走る仕組みを示した理論

アメリカの犯罪学者ドナルド・クレッシーは、不正行為が発生する背景には共通する心理的・環境的な要因があると指摘しました。
人はもともと不正を目的に行動するわけではなく、置かれた環境や状況によって判断が揺らぐことがあります。
その仕組みを整理し、人が不正に至る過程を説明したのが「不正の三要素(トライアングル)」という理論です。
この考え方は、不正を「特定の人の問題」ではなく「誰にでも起こり得る行動」として捉える視点を示しています。
つまり、個人の悪意よりも、心理や環境がどのように影響しているか見極めることが、不正を防止するうえで大切です。
三要素は機会・動機・正当化
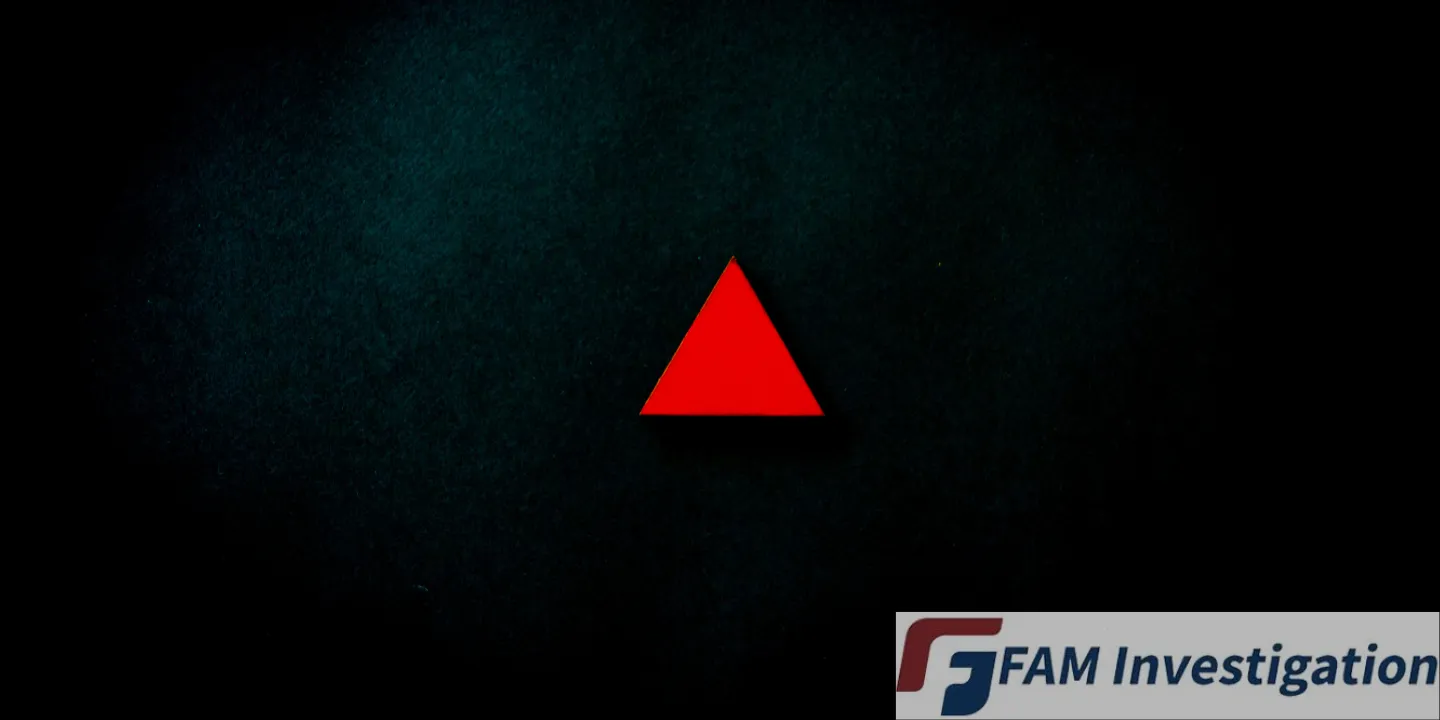
- 機会:不正を実行できる環境や状況
- 動機:不正を行う心理的・経済的な理由
- 正当化:不正を自分の中で許してしまう考え方
不正の三要素は「機会」「動機」「正当化」という三つの条件で構成されています。
どれか一つだけでは不正が成立しにくく、三つがそろったときに行動へ移りやすくなります。
たとえば、お金に困っていて(動機)落ちている財布を見つけた(機会)だけでは、その財布を盗むことはありません。
プラスして「落とした持ち主が悪い」「昔に自分も盗まれたことがある」というような、自分を納得させる材料(正当化)があって行動に移ります。
これが三要素によって不正行為に走ってしまう理論です。
組織における不正防止でも注目を集めている

不正の三要素は、企業の内部統制やリスク管理の分野でも重要な指針として活用されています。
従業員の不正は、個人の倫理観だけでなく、組織の体制や職場環境にも大きく左右されるものです。
そのため、多くの企業ではこの理論をもとに、監査制度の強化や担当する業務の範囲・責任の見直しを行っています。
また、定期的な教育や意識調査を通じて、従業員が不正のリスクを自覚できるようにする取り組みも増えています。
不正の三要素を理解し、組織運営に反映させることで、不正の発生を抑える体制づくりが可能になるでしょう。
[eyechath url="https://www.fam-houjin.jp/reports/embezzlement-insufficient-evidence/"]
業務別に見る「不正三要素」の典型的な具体例
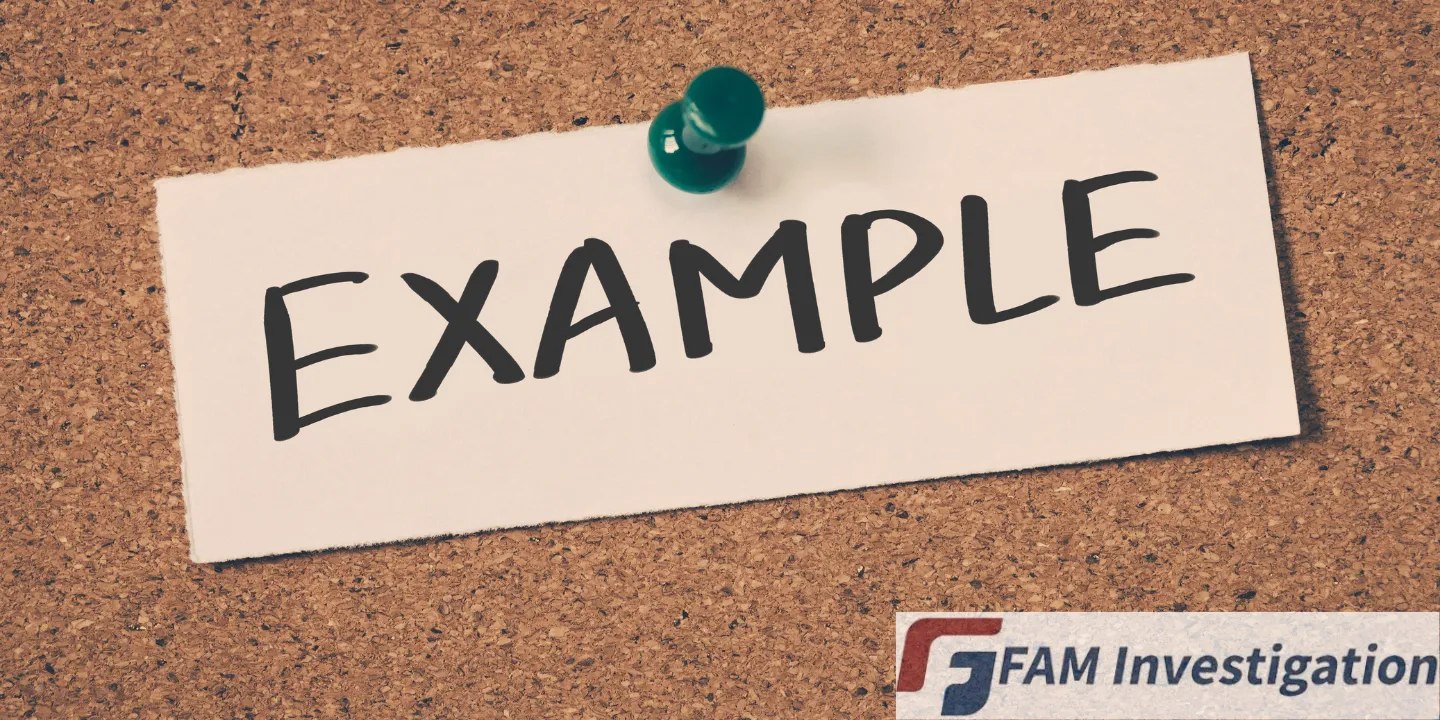
三要素がどのように作用して不正が発生するのか、具体的な例を紹介します。
企業にとって起こり得る例を確認し、より正確に三要素の理解を深めましょう。
経理部門の例:小口現金の使い込み

- 機会:現金管理を一人に任せておりチェック体制が不十分
- 動機:生活費の不足や上司からの過度な業務プレッシャー
- 正当化:「少額だから問題ない」「給料が少ないから」
経理担当者が小口現金を一人で管理していると、支出や残高の確認が形式的になりがちです。
この状況では、日々の支払いを装って少額の不正を重ねても、周囲が気づくのは難しくなります。
結果「少しくらいなら問題ない」という意識が生まれ、不正を正当化してしまいます。
また「給料が少ないから」「成果を認めてもらえないから」と会社への不満から正当化するケースも考えられるでしょう。
こうしたケースを防ぐには、複数人での管理や定期的な照合作業を行うことが重要です。
営業部門の例:成績水増しによる虚偽報告

- 機会:実績確認が自己申告で形式的
- 動機:ノルマへのプレッシャーや評価・昇進への焦り
- 正当化:「周りよりは頑張っているから」「部署のため」
営業担当者は、日々の売上や契約件数を数字で評価されます。
そのため、強い成果プレッシャーを感じると、実際より良い数字を報告したくなる心理が働きます。
特に、報告内容の確認が上司の目視やExcel集計だけの場合、数値の改ざんは容易です。
「部署全体の評価を上げるため」と正当化するケースもありますが、虚偽報告が判明すれば逆に部署全体の信頼を損なう原因にもなります。
防止するためには、第三者による数値照合や、数値以外の行動評価を取り入れることが有効です。
情報システム部門の例:顧客データの持ち出し

- 機会:顧客情報へ自由にアクセスできる
- 動機:転職先への情報提供や、副収入を得るための誘惑
- 正当化:「自分がつくったシステムだから」「退職後に使えば問題ない」
情報システム部門の担当者は、社内ネットワークや顧客データベースに広い権限を持つことが多いです。
そのため、立場を悪用すれば、大量の情報を短時間で持ち出せます。
こうした不正は、発覚した際の被害が特に大きく、企業の信用や取引関係にも深刻な影響を及ぼしかねません。
内部犯行の多くは「自分だけは信用されている」「アクセス権限を与えられているから何をしても良い」という慢心から始まります。
権限の範囲を必要最低限に設定し、操作履歴を定期的に確認するなど、日常的な監視体制を整えることが有効です。
店舗・現場の例:レジ金の抜き取り

- 機会:レジ金の管理を一人に任せ、締め作業のチェックが形骸化している
- 動機:生活費の不足や、給与への不満、長時間労働によるストレス
- 正当化:「休日出勤だから」「残業代が出ないから」
店舗や現場では、レジ金の管理を担当者に任せきりにしているケースは少なくありません。
閉店後のレジ締めを一人で行っていると、不正があってもすぐには発覚しない状況が生まれます。
このような環境では、普段のストレスや不満が引き金となり、不正に手を染めてしまうことがあります。
とくに、休日出勤や残業が続いても十分な手当が支払われていない状況だと、正当化しやすく不正が頻発しかねません。
対策としては、締め作業を複数人で行うほか、金額差異が発生した際の報告ルールを明確にすることが重要です。
不正を未然に防ぐために今すぐできる対策

三要素の理論では、不正は特別な環境や一部の人だけに起こるものではなく、どの職場でも条件がそろえば発生する可能性があります。
そのため、日常業務の中で不正が起こりにくい環境を整えることが大切です。
以下に、不正を未然に防ぐための、すぐに実践できる対策をまとめました。
社内・部署にてできていないものがあればチェックし、実践してみましょう。
金銭の管理は定期的に複数人で行う

経理や店舗など、現金を扱う業務では一人に任せきりにしないことが基本です。
金銭管理を複数人で定期的に確認することで、不正が起きにくい環境をつくれます。
たとえば、出納帳や領収書の照合作業を月ごとに別の担当者がチェックするだけでも、抑止力になります。
また、担当を定期的に入れ替えることも効果的です。
複数の視点が入ることで、不正の「機会」を断ち、透明性の高い管理体制を維持できます。
権限・業務の分離を徹底する

一人の担当者に権限と業務が集中していることが原因の不正も多いです。
たとえば、経理で支払いの承認と振込作業を同じ人物が行うと、不正の「機会」を生みやすくなります。
同様に、顧客管理システムや売上データへのアクセス権限を一人に集中させると、情報の持ち出しや改ざんが起こるリスクも高まります。
承認と実行を別の担当者が行う、またはシステム上で二重確認を設定することで、金銭面・情報面の両方で不正防止につながるでしょう。
人員が限られる小規模な組織でも、最低限の「相互チェック体制」を整えることが大切です。
声を上げやすい職場にする

不満や理不尽さを感じても、それを口にできない職場では、従業員のストレスが蓄積しやすくなります。
やがて「評価されない」「努力が報われない」といった不満が、不正の動機や正当化につながることがあります。
そのため、日常業務や人事、給与面に関する意見を気軽に伝えられる場を設けることが大切です。
たとえば、定期的な面談や匿名の意見フォームなど、立場に関係なく意見を出せる仕組みを整えましょう。
職場全体で意見を受け止め、改善していく風土があれば、従業員の不満を減らし、不正を生みにくい環境をつくることができます。
内部通報制度の信頼性を上げる

内部通報制度は、不正を早期に発見し、再発を防止するための重要な仕組みです。
しかし、制度が存在しても「通報しても改善されない」「通報した人が不利益を受ける」といった不信感があると、機能しなくなります。
そのため、通報内容の秘密保持を徹底し、匿名で相談できる窓口を設けることが重要です。
また、通報後の対応結果を社員に共有することで「制度が実際に機能している」という安心感を生み出せます。
こうした透明性のある運用を続けることで、社員から信頼される通報体制を維持できます。
倫理研修を定期的に行う

不正を防ぐためには、社員一人ひとりが「何が不正にあたるのか」を正しく理解しておくことが欠かせません。
どれほど体制を整えても、倫理意識が浸透していなければ、現場での判断が曖昧になります。
たとえば「得意先だから」「先輩の指示だから」といった理由で、帳簿の修正や経費処理を安易に行ってしまうケースがあります。
定期的に倫理研修やケーススタディを実施し、具体的な事例を通して不正のリスクを共有しましょう。
さらに管理職やリーダー層に対しては、不正を見逃さない姿勢や公平な対応の重要性を共有することも大切です。
知識と意識の両面から社員教育を続けることで、不正の「正当化」を防ぎ、健全な企業風土を育むことができます。
すでに不正が疑われる場合は探偵による証拠収集が大事
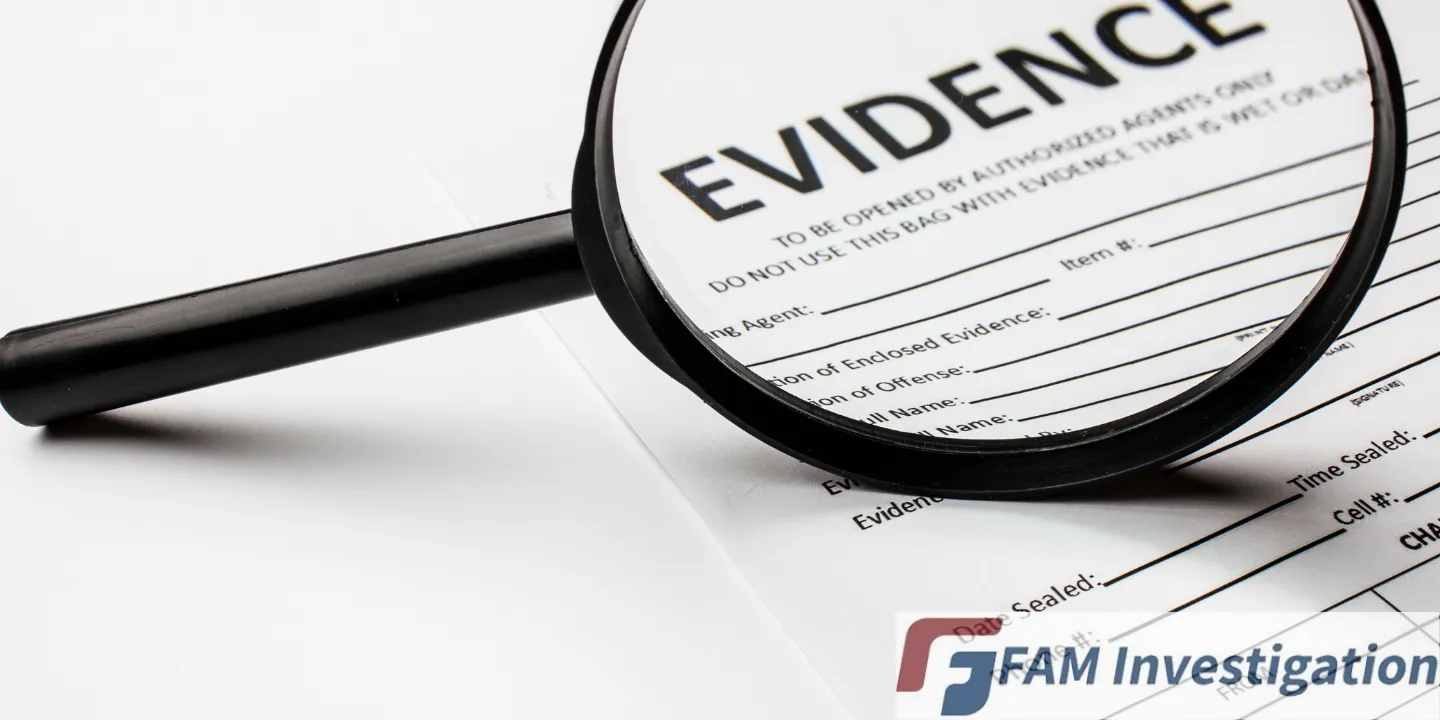
不正がすでに発生している場合には、早期に状況を把握し証拠収集することが重要です。
推測で動くと、証拠が消されるだけでなく、関係者や取引先との信頼関係を損なうおそれがあります。
確実な証拠を得て企業として適切に対応するため、証拠収集のプロである探偵への依頼を検討しましょう。
探偵ができる調査内容

- 従業員の行動・外出先の確認
- 横領時の金銭の追跡調査
- 取引先との接触・癒着の有無の調査
- 領収書・映像などの証拠収集
- 退職者の動向や情報持ち出しの確認
探偵は、主に行動調査や聞き込み調査などを組み合わせて証拠収集が可能です。
たとえば、勤務中の外出や取引先との不審な接触が疑われる場合、現場を確認し、映像や写真で記録します。
横領が疑われるケースでは、対象者を尾行し、不審な金銭の使い道や行動の実態を確認します。
また、対象者が転職した場合、顧客情報や営業資料を不正に利用していないか確認する調査も可能です。
これらの調査結果は、証拠として社内処分や弁護士・警察への提出に活用できます。
探偵の調査費用相場

法人向けの不正調査は、内容や期間、難易度によって費用が大きく異なります。
安い場合は10万円台、内容によっては100万円以上になることもあります。
そのため、探偵事務所に問い合わせて現在の状況を共有し、見積もりを出してもらいましょう。
なお、法人興信所では、165,000円(税込)から不正調査を受け付けております。
不正の内容に合わせて、柔軟にプラン作成いたしますので、ぜひ一度お問い合わせください。
探偵に依頼する際の流れ
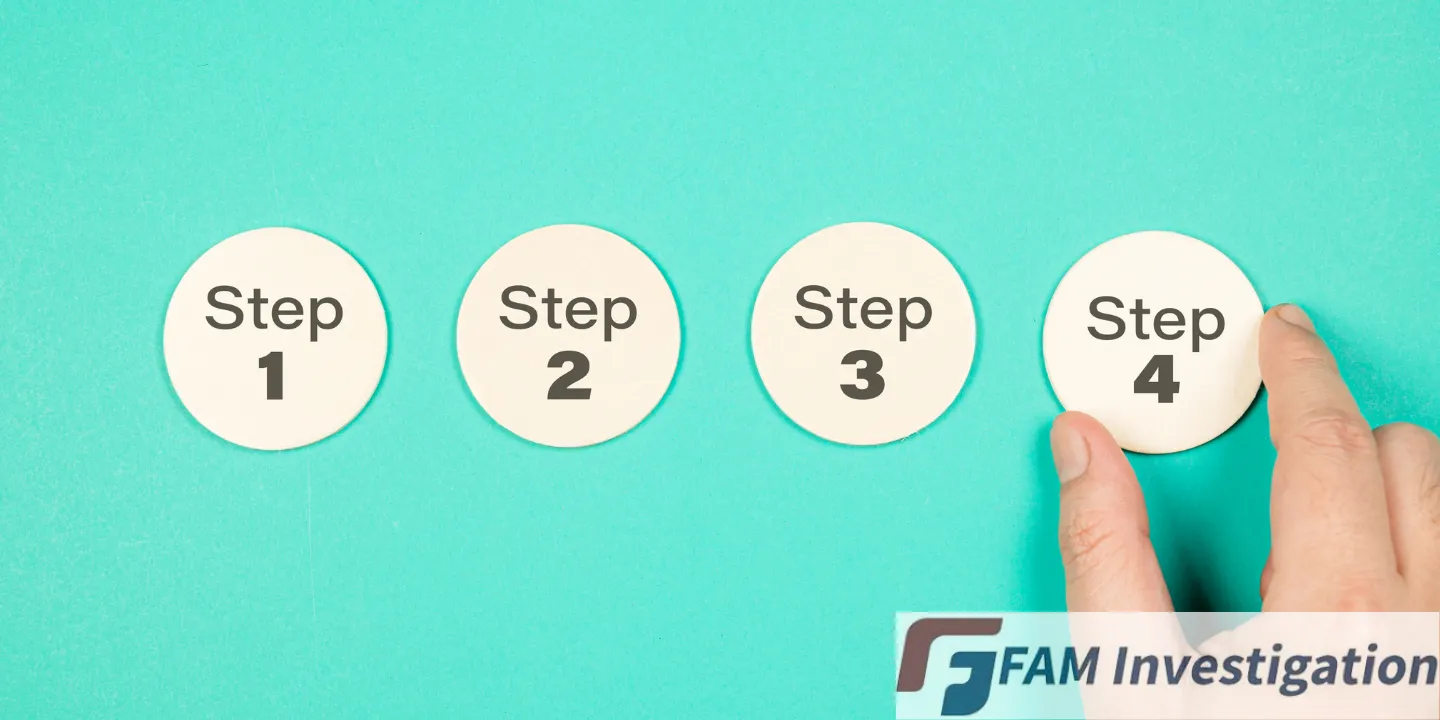
- 相談・ヒアリング
現状の疑い・目的・調査対象を整理し、調査の必要性や方向性の確認を行います。 - 調査プランと見積もりの提示
内容・期間・人員体制をもとに、具体的な調査計画と見積もりが提示されます。 - 契約・調査開始
契約内容を確認後、調査を実施。行動確認・聞き込み・資料収集などが行われます。 - 経過報告・中間確認
長期調査の場合は途中経過を共有し、必要に応じて調査方針が調整されます。 - 報告書の提出・アフターフォロー
調査終了後、写真や行動記録をまとめた報告書が提出されます。
探偵に依頼し調査が完了するまでの大まかな流れは上記の通りです。
法的対応を検討している場合は、弁護士を紹介してもらえる探偵事務所を選ぶとよりスムーズに進められます。
証拠は時間経過とともに確保しにくくなるため、不正の疑いがある場合は、まずは探偵に相談し今後の方針を決めましょう。
社内不正調査は法人興信所にお任せください

社内で不正が疑われる場合、今後の信用に大きく関わるため、探偵に依頼し早期に証拠収集・対処をすることが大事です。
法人興信所では、企業における内部不正や情報漏えいなど、法人向け調査にも対応しています。
長年の経験と実績をもとに、これまで多くの企業様からご相談をいただき、93%という高い顧客満足度を維持しております。
社内での不正が疑われる場合は、まずはお気軽にご相談ください。
問題の早期解決と、企業の信頼回復に向けて全力でサポートいたします。
ご相談とご依頼までの流れ
-
まずはフリーダイヤル・お問い合わせメールフォーム・LINEよりお問い合わせ下さい。問題の概要や状況をお聞き致します。
-
無料面談にて、電話やメール、LINEにて無料相談頂いた内容の詳細をお聞きし、お手伝い出来る調査やサポートをご提案致します。その際、お見積りをご提示致します。
お見積り内容には、調査期間・調査員数・調査方法・調査報告書の作成費などが含まれています。 -
お見積り金額・調査内容に十分ご納得頂けた場合、委任契約のお手続きに入ります。下記書面に署名捺印をして頂き、契約完了となります。書面には、調査目的・期間・費用の詳細・調査結果の報告方法・個人情報の取り扱いなどが記載されています。
-
契約書面を基に予備調査、本調査の順に調査を実施します。その際、随時途中経過をご報告致します。追加調査が必要な場合は、都度ご相談下さい。
-
全ての調査終了後、書面もしくはデータにて調査報告書を提出致します。必要に応じて各種専門家のご紹介やアドバイスなどのアフターサービスも行なっております。
お問い合わせ
ご相談は、プライバシー 秘密事項厳守で承ります。
クレジット決済のご案内
お支払い方法について、銀行振込のほか、各種クレジットカードにも対応しております。
ご都合のよい方法をお選びいただけます。
クレジットカード決済は、テレコムクレジット株式会社にて、おこなっております。
※ ご利用者様のクレジットカードの内容はSSLにて厳重に保護されます。
※ 提供サービスの特性上、決済後の返金はお受け出来かねます。